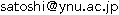|
所属組織 |
大学院都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 |
|
職名 |
教授 |
|
生年 |
1962年 |
|
研究キーワード |
日本建築史、保存修復 |
|
メールアドレス |
|
|
関連SDGs |
代表的な業績 【 表示 / 非表示 】
-
【著書】 伊勢山皇大神宮本殿造営事業における建築工事報告書(伊勢山皇大神宮) 2024年08月
【論文】 正倉院漆六角厨子復元考察(正倉院紀要) 2023年03月
【論文】 群馬県島村における近世末~近代初期の養蚕農家主屋の開口部変化 2016年06月
直近の代表的な業績 (過去5年) 【 表示 / 非表示 】
-
【著書】 田島弥平旧宅10周年記念シンポジウム記録および境島村登録文化財活用推進協議会総会講演資料(私家版) 2025年03月
【著書】 伊勢山皇大神宮本殿造営事業における建築工事報告書(伊勢山皇大神宮) 2024年08月
【論文】 正倉院漆六角厨子復元考察(正倉院紀要) 2023年03月
【著書】 群馬県近世寺社建総合調査報告書 ―歴史的建造物を中心に―《本編》 2022年03月
【著書】 若宮大路周辺遺跡群(No.242)ふれあい鎌倉ホスピタル建替え工事に伴う発掘調査 鎌倉市御成町778番1他13筆 2021年11月
学内所属歴 【 表示 / 非表示 】
-
2014年10月-現在
専任 横浜国立大学 大学院都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 教授
-
2011年4月-2014年9月
専任 横浜国立大学 大学院都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 准教授
-
2007年4月-2011年3月
専任 横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
-
2001年4月-2007年3月
専任 横浜国立大学 大学院工学研究院 助教授
-
1998年10月-2001年3月
専任 横浜国立大学 工学部 助教授
学外略歴 【 表示 / 非表示 】
-
1991年7月-1998年9月
川崎市立日本民家園 技術職員
-
1984年4月-1991年6月
財団法人文化財建造物保存技術協会 技術職員
研究経歴 【 表示 / 非表示 】
-
伝統民家継承に関する手法研究―理念と技術伝承を通じた共通認識涵養をめざして―
科学研究費補助金
研究期間:
-
歴史的建造物の保存修理技術(調査・設計・監理)に関する基礎的研究
研究期間:
-
日本建築史の再構築
科学研究費補助金
研究期間:
-
相模原市協働事業 古民家ツアーを通じた歴史的資産の保存活用手法の実践
その他の研究制度
研究期間:
-
境島村における幕末~近代の蚕種製造民家群の保存継承に関する基礎的研究
科学研究費補助金
研究期間: 2021年4月 - 2025年3月
著書 【 表示 / 非表示 】
-
田島弥平旧宅10周年記念シンポジウム記録および境島村登録文化財活用推進協議会総会講演資料
大野敏( 担当: 単著 , 範囲: 編集・全文執筆)
私家版 2025年3月
総ページ数:41 担当ページ:41 記述言語:日本語 著書種別:その他
-
伊勢山皇大神宮本殿造営事業における建築工事報告書
大野敏(阿久津裕司・小沢朗・利根伸介・中島英孝)( 担当: 共著 , 範囲: 監修・編集、執筆項目多数)
伊勢山皇大神宮 2024年8月
総ページ数:190 記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
群馬県近世寺社建総合調査報告書 ―歴史的建造物を中心に―《本編》
大野敏、大橋竜太、佐藤孝之、丑木幸男、上野勝久、村田敬一、小林正( 担当: 共著 , 範囲: 第3章 総論)
群馬県 2022年3月
総ページ数:321 担当ページ:121-143 記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
若宮大路周辺遺跡群(No.242)ふれあい鎌倉ホスピタル建替え工事に伴う発掘調査 鎌倉市御成町778番1他13筆
大野敏、濱村友美、青木誠、兼康保明、齋藤紀行、高橋敦、米田譲、尾嵜大真、大森貴之、奈良貴史、佐伯史子、上本進二( 担当: 共著 , 範囲: 第7章まとめ 第1節 検出した竪穴建物と井戸に関する建築史的所見)
株式会社イビソク 2021年11月
総ページ数:210 担当ページ:156-194 記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
横浜の茅葺き建築 茅葺きに学ぶエコロジー
大野敏( 担当: 単著 , 範囲: 序文と表紙を除くすべての本文と写真。図版の半分を担当。一部図面は張カシ氏の担当。)
公益財団法人 横浜歴史資産調査会 2020年3月
総ページ数:31 担当ページ:2,4-31 記述言語:日本語 著書種別:その他
ヨコハマヘリテイジが市内の建築の魅力を伝えるブックレットの第三編として発行した解説書。横浜市内に残る茅葺き建築について、民家を以中心に紹介した。内容は、まず茅葺き建築文化についての基本的事項をQ&A形式で説明した。ついで、横浜市内の茅葺き民家調査の概要を踏まえ、茅葺き民家の存続手法を所有と公開形態をもとに類型別に説明した。この際に神奈川県下の事例も紹介しながら横浜市における歴史的建造物保存継承手法の特色を示した。また、民家以外の茅葺き建築についての紹介と、茅葺き屋根の防火についても説明を加えた。
学位論文 【 表示 / 非表示 】
-
古代・中世厨子の形態に関する建築的研究
大野敏
1998年3月
未設定 単著 [査読有り]
おもに仏堂内に安置されて本尊を祀る厨子に関して、その形態に着目して古代~中世前半までにおける遺例を整理分類した。そして史料分析も加味して古代においてはその原形が建築(宮殿)・帳房・天蓋・棚の4種に由来すると解き、中世前期までに新たな形式(山華焦葉系)が中国から伝来したとし、中世は宮殿系厨子、円形天蓋系厨子、箱・筒系厨子、天蓋帳房折衷厨子、宮殿天蓋折衷厨子、山華焦葉系厨子、計6系統の厨子が存在することを示した。そして室町前期を境に本尊厨子は帳房天蓋折衷系厨子から宮殿系厨子に主流が転換すること、この時期は宮殿系厨子の規模・意匠において一大高揚期であったことを示した。総ページ数157。
論文 【 表示 / 非表示 】
-
民家の保存修理技術[調査・設計・監理]
大野敏
2023年度日本建築学会大会(近畿) 建築歴史・意匠部門 パネルディスカッション-1 資料『民家研 究の新視点』 33 - 44 2023年9月
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 単著
-
正倉院漆六角厨子復元考察
大野敏
正倉院紀要 ( 45 ) 47 - 90 2023年3月
担当区分:筆頭著者, 責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要) 単著
-
田島弥平旧宅新蚕室の平面と構造に関する復元考察
チェン・スイ・イー,大野敏
日本建築学会技術報告集 28 ( 70 ) 1551 - 1556 2022年10月 [査読有り]
担当区分:最終著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 単著
-
個人所有重文民家の修理および維持管理費用の実態と課題-重文民家の所有者を対象とした調査から-
碓田智子,中尾七重,大野 敏, 栗本康代
住宅系研究報告会論文集 ( 17 ) 135 - 144 2022年12月 [査読有り]
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 単著
-
大野敏
日本建築学会技術報告集 第 27 巻 ( 第 67 ) 1500 - 1505 2021年10月 [査読有り]
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 単著
その他リンク: https://www.jstage.jst.go.jp/article/aijt/27/67/27_1500/_pdf/-char/ja
総説・解説記事等 【 表示 / 非表示 】
-
魅力知り継承の契機へ ―群馬のソウルハウス―(上毛新聞「オピニオン21 視点」)
大野敏
上毛新聞 2024年10月 [依頼有り]
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア) 単著
-
次の10年へ整備推進を ―田島弥平旧宅と境島村―(上毛新聞「オピニオン21 視点」)
大野敏
上毛新聞 2024年7月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア) 単著
-
重伝建の街づくり推進―境島村の養蚕建築群―(上毛新聞「オピニオン21 視点」)
大野敏
上毛新聞 2024年6月 [依頼有り]
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア) 単著
-
活動支える地域の底力―ぐんま島村蚕種の会―(上毛新聞「オピニオン21 視点」)
大野敏
上毛新聞 2024年4月 [依頼有り]
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア) 単著
-
文化遺産の公開 魅力伝える交流大切に(上毛新聞「オピニオン21 視点」)
大野敏
上毛新聞 2024年2月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア) 単著
作品・芸術・データベース等 【 表示 / 非表示 】
-
第75回正倉院展「よみがえる幻の厨子」にて研究成果紹介
奈良国立博物館
2023年10月 - 2023年11月
作品分類:その他 発表場所:奈良国立博物館
-
コレクション展 横浜正金銀行本店本館
大野敏・(守田正志・菅野裕子・藤岡泰寛ほか)
2024年11月 - 2024年12月
作品分類:その他 発表場所:神奈川県立歴史博物館
-
横浜市西教寺本堂所見
大野敏
2024年11月
作品分類:その他
-
神奈川県指定文化財 旧青柳寺庫裏屋根葺替修理事業に修理設計に関する技術指導
大野敏
2017年4月 - 2019年3月
作品分類:その他 発表場所:所在地は相模原市大島
茅葺屋根の葺替修理設計の事前指導、修理設計内容確認と指導、修理時における技術指導を継続的に行い、相模原市建築関係職員に対する現地説明会講師も引き受けた。
-
森家住宅保存修理工事基本設計(村田重要伝統的建造物群保存地区内)
大野敏
2015年2月
作品分類:建築作品
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
境島村における幕末~近代の蚕種製造民家群の保存継承に関する基礎的研究
2020年4月 - 2025年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
代表者:大野敏
資金種別:競争的資金
世界遺産の登録とその保存整備事業進展の一方で、島村の蚕種製造民家に関する基本的知見(蚕種製造工程と蚕室空間の対応関係、集落毎の蚕種製造住宅の成立・展開事情の把握、近隣との影響関係)は、解明すべき事柄がまだ存在する。何より約80件近く残存する遺構のうち詳細調査された事例が14件にとどまっている点は問題である。
この課題に対して、調査件数の拡大をはかり既存調査事例の見直しを含めて基礎資料の充実を図る。 -
歴史的建造物の保存修理技術(調査・設計・監理)に関する基礎的研究
2016年4月 - 2020年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
代表者:大野敏
資金種別:競争的資金
本における伝統木造建築を中心とする歴史的建造物の継承策は、国の重要文化財制度を頂点として重要伝統的建造物群保存地区選定制度(昭和50年)・登録有形文化財制度(平成8年)に拡がりを見せ、こうした中で維持保存施策が厳格に行われる重要文化財は、専門の修復建築家によって膨大な手間と資金(補助金)を費やして丁寧に維持修理が行われ、建築基準法の適用も受けない。しかし、重要文化財以外の文化財建造物は、維持修理に当たって文化遺産的価値をどこまで継承するのかの判断が多様で、厳しい財源の中で建築基準法にも配慮しながら維持修理に臨むことが多い。まして文化財未指定の歴史的建造物は、それ以上に維持継承に対する選択肢が多様である。すなわち重要文化財以外の歴史的建造物は、その継承手法が多様で複雑である。
一方、歴史的建造物の継承に関わる人材育成は、阪神大震災以後ヘリテイジ・マネージャー制度が全国に拡がり、一般の建築家や古建築愛好家が歴史的建造物に関心を持つ機会が増えてきた。こうした人材が非重要文化財の歴史的建造物継承の中核として期待されている。
つまり、新たな人材層に対して、多様で複雑かつ事例増加が見込まれる非重要文化財の歴史的建造物継承への対応を期待しているといえる。
現在のところヘリテイジ・マネージャー修了生の多くは、歴史的建造物の価値を見いだす業務段階にとどまっている場合が多いが、いずれは維持修理への参画が本格化する事は間違いない。その際に具体的な対処法として参照すべき資料はきわめて少ない。すなわち、当該建物の破損状況把握、その原因探求、具体的な対処法とそれによる文化遺産的価値の継承度合、工事費の積算根拠、などの具体的事例を収集・整理して提示することが強く求められている。
本研究は、申請者の文化財修復技術者としての経験と、研究者として全国の歴史的建造物調査や保存施策・人材育成講座などに関わってきた経験を総合して、様々なカテゴリーの文化財建造物の保存修理事例の集積と分析整理を行い、具体的な保存修復に向けての基礎資料を提供する -
災害で埋没した建物による民家建築史の研究
2020年4月 - 2025年3月
科学研究費補助金 基盤研究(A)
代表者:箱崎和久
資金種別:競争的資金
災害で埋没した建物を埋没建物と呼ぶが、埋没建物は、建築の下部が建ったまま、あるいは倒壊して部材が組み合ったまま残るのが特徴で、発掘調査で見つかる建物跡(遺構)よ
り圧倒的に建築的情報が多い。研究対象とするのは、①6世期の群馬県、②10世期の秋田県、③18世期の群馬県で、とりわけ③は広域の発掘調査により敷地ごと発見されており、
当時の主屋・付属屋・畑などを含む集落の実態が判明する。一方、民家史研究は、現存する社会的階層の高い民家をもとに構築されてきた。現存しない竪穴建物や掘立柱建物、社
会的中下層の民家については、「遺構」からうかがうしかなかった。被災埋没建物の検討により、それらの建物の実態が判明する。また現存古民家を悉皆調査することで、これま
では十分取り上げられてこなかった中下層の民家の存否をあきらかにし、被災埋没建物と比較検討をおこなう。これらによって民家史を再構築する。ここから判明する民家史は、一部の地域に限定されるものかもしれないが、これまでよりも多彩で、「遺構」からうかがうことができる民家のイメージを豊かにすることができる。 -
被災・破損を中心とする建設の技術革新と建築様式に関する歴史的研究
2013年4月 - 2018年3月
科学研究費補助金 基盤研究(A)
代表者:藤井恵介
資金種別:競争的資金
建築史において、様式変化の要因として構造技術の発展が重要な位置を占める.その契機として過去の被災により建築物のダメージに対するイノベーション(技術革新)の意味合いが無視できない。この視点に立って、現在の建築様式における技術革新の果たした役割をあらためて把握し、客観的な評価をおこなう。
-
伝統民家継承に関する手法研究-理念と技術伝承を通じた共通認識涵養をめざして-
2011年4月 - 2014年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
資金種別:競争的資金
その他競争的資金獲得・外部資金受入状況 【 表示 / 非表示 】
-
茅葺き技術の伝承手法に関する研究 ~記録の重要性に注目して~
2022年4月 - 2023年3月
公益財団法人 松井角平記念財団 公益財団法人 松井角平記念財団 助成金
代表者:大野敏
担当区分:研究代表者
本研究は以下の 3 項目で構成する。
1.申請者が過去に関わってきた茅葺き建物調査と屋根葺き工事に関する資料の総括。
2.修理工事報告書における茅葺き工事の記録の確認と内容整理
3.茅葺き技術保存に関する活動の確認調 -
正倉院所蔵の紫檀塔部材および黒漆塗六角厨子部材の復原的考察
2020年4月 - 2021年9月
公益財団法人 松井角平記念財団 公益財団法人 松井角平記念財団 研究助成
代表者:大野敏
正倉院宝物の中には、原形をとどめない残欠と呼ばれる資料が存在する。宮内庁正倉院事務所では、こうした資料についても丁寧に保管しながら、本来形式の把握について着実に調査研究を進めている。
こうした調査研究中の資料の中に紫檀塔残欠と黒漆塗六角厨子部材がある。前者は建築史学の泰斗・浅野清博士により部材の整理と復原考察がなされたが、未解明の部分が少なくない。後者は正倉院事務所において復原考察がなされているが、細部のおさまりの確定と復原図の作成には至っていない。
大野敏・春日井道彦・箱崎和久は正倉院事務所のご厚意により、2017年10月に上記資料を実見する機会を得て、その実態を知ることができた。その経験をもとに、以下のような確認調査と復原検討の研究を企画した。
すなわち、紫檀塔については、浅野清博士により海竜王寺五重小塔のように外部のみ建築的に作る箱式構造の5重小塔の可能性が指摘され、組物の部分的な復原図が提示されている。ただし柱間寸法や塔全体の形状に関しては復原図などの具体像は提示されていない。この点について、組物、垂木、隅木、茅負、高欄といった部材の再確認の中から、①各部材の寸法比例から5層で確定しうるか、②組物復原は妥当か、③軒構造についての解明はどこまで可能か、④上記の検討の結果により平面図・断面図・立面図の作成は可能なのか、を見極めたい。また、黒漆塗六角厨子部材に関しては、柱の上下の判断が重要であるが、上下の解釈に従って2種類の復原案を作成することにより、その妥当性を検証してみたい。
以上本研究は、異例の少ない奈良時代の建築・工芸の意匠と技法を解明するうえで重要な基礎的研究であり、今までの知見を深めるという点で意義が高い。 -
近代の文化財建造物の保存活用に関する基礎的研究ー神奈川県立博物館(旧横浜正金銀行本店本館)を事例として
2019年4月 - 2020年3月
公益財団法人松井角平記念財団 公益財団法人松井角平記念財団研究助成
代表者:大野敏
神奈川県立博物館は旧横浜正金銀行本店本館(明治38年 設計妻木頼黄)を博物館に転用した建物で、日本を代表する明治末期の近大建築として重要文化財に指定されている。この建物は鉄材で補助的に用いたレンガ造(一部石造)建築で、関東大震災時も崩壊しない頑健さを誇ったが,屋頂ドーム(銅板張.鉄骨及び木造)が火災に遭ったため、屋内も被災し,大正末期に大がかりな修理を経ている。その実態の解明はまだ十分でない。また創建時の図面も簡単なものが残されているに過ぎない。したがって本研究では、本店本館の建築に関して、大正改修の実態把握(資料整理と実測)を通して建築当初形式の残存状況を把握することにより、基礎資料を整備することを目指す。
-
歴史的資産を活用した外国人観光客誘客に資する相模原市観光振興の具体的提案移換する調査研究
2017年11月 - 2018年2月
相模原市観光協会 調査委託費
代表者:大野敏
ふじの里山くらぶと横浜国立大学が連携して毎年一回実施してきた「古民家ツアー」14回分のアンケート結果を整理し資料化した.また、その内容を踏まえ、昨年度の調査成果(外国人留学生が日本の伝統文化をどのように享受したいか)も参照して、ツアー案を企画するとともに、具体的名体験メニューとして習字とコースター造りをあわせた提案を行った。
-
歴史的資産を活かした観光振興のための基礎研究「ルートと解説の提案」
2016年12月 - 2017年3月
相模原市観光協会
代表者:大野敏
研究発表 【 表示 / 非表示 】
-
田島弥平旧宅世界遺産登録10年の成果と課題
大野敏 [招待有り]
世界遺産田島弥平旧宅10周年記念シンポジウム 2024年7月 伊勢崎市・伊勢崎市教育委員会
開催年月日: 2025年7月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:群馬県伊勢崎市 国名:日本国
-
群馬県における近世・近代民家と吾妻郡の民家
大野敏
群馬県近世・近代民家シンポジウム 〜吾妻の民家を中心として〜 2024年10月 「災害で埋没した建物による民家建築史の研究」 チーム(代表: 箱崎和久)
開催年月日: 2024年10月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:群馬県前橋市 国名:日本国
企画及び講演および討論会司会
令和6年10月13日(日) 13時〜16時30分
場所:群馬県公社ビル1階西研修室
参加者80名 -
三溪園における古建築の保存・継承について
大野敏 [招待有り]
第60回文化財指定庭園保護協議会 総会 2023年6月 文化財指定庭園保護協議会
開催年月日: 2023年6月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(招待・特別)
開催地:横浜市
-
民家野外博物館に期待すること 川崎市立日本民家園の実績ほかを通して考える
大野敏
2024 年度 全国文化財集落施設協議会総会 記念講演 2024年12月 全国文化財集落施設協議会
開催年月日: 2024年12月
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:川崎市
-
横浜の茅葺き
大野敏 [招待有り]
全国民家集落施設協議会総会 2023年12月 全国民家集落施設協議会
開催年月日: 2023年12月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(招待・特別)
開催地:横浜市 国名:日本国
共同研究希望テーマ 【 表示 / 非表示 】
-
歴史的建造物の保存技術の継承に関して
-
歴史的建築遺産の発掘とそれを活かしたまちづくりに関して
-
伝統的木造建築の保存・修復および活用について
共同・受託研究情報 【 表示 / 非表示 】
-
長野県安曇野市所在の等々力家住宅に関する建築史的研究
提供機関: 等々力家 その他
研究期間: 2009年10月 - 2017年3月
-
指物(指付け技法)の変遷過程と歴史的木造架構の類型化に関する研究
国内共同研究
研究期間: 2000年04月 - 2004年3月
-
木造建造物の保存修復のあり方と手法
国内共同研究
研究期間: 1998年12月 - 2003年3月
担当授業科目(学内) 【 表示 / 非表示 】
-
2025年度 建築芸術史論A
都市科学部
-
2025年度 建築芸術史論B
都市科学部
-
2025年度 絵画・彫塑・基礎デザインⅣ
都市科学部
-
2025年度 日本建築史Ⅰ
都市科学部
-
2025年度 日本建築史Ⅱ
都市科学部
その他教育活動及び特記事項 【 表示 / 非表示 】
-
2024年04月-現在横浜市歴史博物館との博学連携活動 (教育方法・実践に関する発表、講演)
-
2018年04月-現在神奈川県立歴史博物館との博学連携 (その他特記事項)
-
2021年04月-現在「羽沢横浜国大駅周辺とキャンパスを都市科学する」プロジェクト推進 (その他特記事項)
-
2018年08月-2018年10月弘前市における歴史的建造物の魅力(古民家、庭園、近代建築)ポスター発表 (教育方法・実践に関する発表、講演)
委員歴 【 表示 / 非表示 】
-
平城宮跡及び藤原宮跡等の保存整備に関する検討委員会
2025年01月 - 現在 平城宮跡及び藤原宮跡等の保存整備に関する検討委員会委員
委員区分:政府
-
史跡等における歴史的建造物の復元の取扱いに関する専門委員会
2023年07月 - 現在 専門委員会委員
委員区分:政府
-
群馬県文化財保護審議会
2014年08月 - 現在 審議会委員(建造物部会所属)
委員区分:自治体
-
横浜市文化財審議会
2010年09月 - 現在 審議会委員副会長(建造物部会所属 建造物部会長)
委員区分:自治体
-
文化審議会文化財分科会第二専門調査会
2017年04月 - 2024年5月 第二専門調査会委員
委員区分:政府
主に文化財建造物に関する新規の指定・選定・登録案件に関して専門的立場から見を述べる.また、重要文化在建造物の保存修理における現状変更に関して専門的立場から意見を述べる
社会活動(公開講座等) 【 表示 / 非表示 】
-
鹿児島県建築士会ヘリテージマネージャ講習会
役割:講師
鹿児島県建築士会 2025年3月
対象: その他
種別:資格認定講習
鹿児島県建築士会主催のヘリテージマネージャ講習会の講師として、鹿児島県加世田重要伝統的建造物群保存地区内の文化財住宅を対象として、平面実測調査と建築の特徴を把握する調査演習の講師を務めた。
-
横須賀の万代会館と永島家長屋門
役割:講師
(公財)横須賀市生涯学習事業団 2024年度 横須賀市民大学(後期講座)「近代の住宅建築と神奈川の民家保存の特徴」 2025年1月
-
神奈川県の民家保存の特徴(横浜と川崎を中心に)
役割:講師
公財)横須賀市生涯学習事業団 2024年度 横須賀市民大学(後期講座)「近代の住宅建築と神奈川の民家保存の特徴」 2025年1月
-
旧横浜正金銀行本店本館研究の最前線 〜博物館と大学の博学連携を通して〜
役割:講師
神奈川県立歴史博物館 県博セミナー 「旧横浜正金銀行本店本館の現在と未来」第1回 2024年12月
-
横浜の茅葺き建築
役割:講師
横浜市歴史博物館 横浜市歴史博物館 青葉・都筑区制30周年「丘のよこはま-近代の村の歴史とくらし-」 関連講座 2024年11月
メディア報道 【 表示 / 非表示 】
-
吾妻の養蚕古民家 建築遺産として光
上毛新聞社 上毛新聞 2024年10月
執筆者:本人以外
-
田島弥平旧宅記念シンポ伊勢崎 島村の在り方探る
上毛新聞社 上毛新聞 2024年7月
執筆者:本人以外
-
「幻の厨子」の姿明らかに 第75回正倉院展
読売新聞社 読売新聞 読売新聞奈良県版 2023年11月
執筆者:本人
-
田島弥平旧宅世界遺産登録9周年フェスタ クイズスタンプラリー
上毛新聞社 上毛新聞「三山春秋」 コラム「三山春秋」 2023年7月
執筆者:本人以外
-
BS 朝日 百年名家 「島村養蚕農家群」
BS朝日 百年名家 2021年9月
執筆者:本人
学術貢献活動 【 表示 / 非表示 】
-
日本伝統建築技術保存会 文化財木工技能者 技能研修会(講座)
役割:企画立案・運営等, 審査・評価, 保存・修復, その他
日本伝統建築技術保存会 ( 八王子セミナーハウス講義室 ) 2023年1月
種別:文化財保護
国選定保存技術である文化財木工技能保持団体である日本伝統建築技術保存会では、文化財木工技能者の養成研修を普通コースと上級コースに分けて実施している。普通コースでは座学による研修と、実地による木組加工と古建築調査の演習を設けいる。2022年度の東日本における講座のうち、「日本伝統建築技能研修 前期 古建築修理Ⅰ-1および古建築修理Ⅰ-2」を担当して講義した。内容は、歴史的木造建築の特性と修理の必要性。履歴把握・破損要因・日常管理の重要性
に注目しながら具体的事例をもとに教授。 -
日本伝統建築技術保存会 文化財木工技能者 技能研修会(調査演習)
役割:企画立案・運営等, 審査・評価, 保存・修復, その他
日本伝統建築技術保存会 ( 横浜三溪園 重要文化財月華殿 ) 2022年8月
種別:文化財保護
国選定保存技術である文化財木工技能保持団体である日本伝統建築技術保存会では、文化財木工技能者の養成研修を普通コースと上級コースに分けて実施している。普通コースでは座学による研修と、実地による木組加工と古建築調査の演習を設けいる。2022年度の東日本における調査演習は、横浜三溪園の重要文化財月華殿の平面調査をおこない、古材の残存状況や改造の経緯などにも配慮した調書作成手法を教授した。
学内活動 【 表示 / 非表示 】
-
2024年04月-2026年3月全学業績評価委員会小委員会 (全学委員会)
-
2023年04月-2026年3月教育検討委員会 (部局内委員会)
-
2023年04月-2026年3月副研究院長 (部局内委員会)
-
2023年04月-2026年3月部局災害対策本部委員(施設対策班班長) (部局内委員会)
-
2023年04月-2026年3月先進実践学環代議員 (部局内委員会)