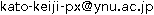|
所属組織 |
教育学部 学校教員養成課程 理科教育 |
|
職名 |
教授 |
|
研究キーワード |
科学教育、教科教育学 |
|
メールアドレス |
|
|
ホームページ |
|
|
関連SDGs |
代表的な業績 【 表示 / 非表示 】
-
【論文】 科学概念構築過程における「俯瞰する行為」の思考要素に関する実践的検討―中学校理科授業における生徒の思考過程の分析をもとにして―(科学教育研究) 2021年02月
【論文】 科学的知識の統合・創発を支援する立体型イメージマップの開発と評価(理科教育学研究) 2023年07月
【著書】 小学校理科を教えるために知っておきたいこと 初等理科内容学と指導法(東洋館出版社) 2022年01月
直近の代表的な業績 (過去5年) 【 表示 / 非表示 】
-
【論文】 科学的知識の統合・創発を支援する立体型イメージマップの開発と評価(理科教育学研究) 2023年07月
【論文】 科学概念構築過程における「俯瞰する行為」の思考要素に関する実践的検討―中学校理科授業における生徒の思考過程の分析をもとにして― 2020年12月
【著書】 小学校理科を教えるために知っておきたいこと 初等理科内容学と指導法(東洋館出版社) 2022年01月
【論文】 対話を基軸とした中学校理科の問題解決過程における知識統合の実態 2021年03月
【論文】 「科学の本質(NOS)」の創造的な理解を促す授業デザイン開発に資するアクションリサーチ(理科教育学研究) 2024年03月
学歴 【 表示 / 非表示 】
-
-2011年3月
兵庫教育大学 学校教育研究科 教科教育実践学専攻 博士課程 修了
-
-1987年
東京学芸大学 教育学研究科 理科教育 修了
-
-1984年
愛知教育大学 教育学部 小学校教員養成課程 卒業
学内所属歴 【 表示 / 非表示 】
-
2024年4月-現在
併任 横浜国立大学 その他 附属図書館 館長
-
2021年4月-現在
専任 横浜国立大学 教育学部 学校教員養成課程 理科教育 教授
-
2017年4月-2021年3月
専任 横浜国立大学 教育学部 学校教育課程 理科教育 教授
-
2010年4月-2017年3月
専任 横浜国立大学 教育人間科学部 学校教育課程 理科教育 教授
-
2007年4月-2010年3月
専任 横浜国立大学 教育人間科学部 学校教育課程 理科教育 准教授
学外略歴 【 表示 / 非表示 】
-
2015年2月-2019年11月
愛知教育大学 大学院教育学研究科 非常勤講師
-
2004年4月-現在
日本女子大学 理学部 非常勤講師
-
2003年9月-2006年10月
愛知教育大学 教育学部 非常勤講師
-
2003年1月-2008年9月
静岡大学 理学部 非常勤講師
-
2000年9月-現在
文部省新教育学研究科設置審査マル合 /
著書 【 表示 / 非表示 】
-
小学校理科を教えるために知っておきたいこと 初等理科内容学と指導法
安部洋一郎,小川博士,加藤圭司,高橋信幸,中島雅子,名倉昌巳,平田豊成,松本栄次,向井大喜,山岡武邦( 担当: 共著 , 範囲: 加藤圭司)
東洋館出版社 2022年1月 ( ISBN:978-4-491-04722-5 )
総ページ数:237 担当ページ:8-19 記述言語:日本語 著書種別:教科書・概説・概論
-
小学校理科教育法
森本信也、森藤義孝、大貫麻美、小川哲男、小野瀬倫也、甲斐初美、加藤圭司、黒田篤志、坂本憲明、佐藤寛之、辻健、宮野純次、三好美織、八嶋真理子、和田一郎、渡辺理文( 担当: 共著)
建帛社 2018年4月 ( ISBN:9784767921105 )
総ページ数:220 担当ページ:15 記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
新訂 理科教育入門書 平成29年度版学習指導要領対応
松森靖夫、森本信也、和田一郎、加藤圭司、黒田篤志、佐藤寛之、小野瀬倫也、佐々木智謙、渡辺理文( 担当: 分担執筆)
東洋館出版社 2018年3月 ( ISBN:9784491034881 )
総ページ数:165 担当ページ:18 記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
「見通す・振り返る」学習活動を重視した授業事例集
加藤圭司 他22名( 担当: 共編者(共編著者))
学事出版 2015年3月 ( ISBN:978-4-7619-2109-5 )
総ページ数:126 担当ページ:2-3 記述言語:日本語 著書種別:学術書
附属横浜中学校では、前年度までの研究において、学習意欲に支えられて展開していく充実した言語活動の背景に、生徒自身による各自の学びを見定めようとする姿があることを明らかにできた。このことを踏まえ、生徒の主体性と自律性をより活かす方向で授業構築を進めることを目指して、「見通す・振り返る」学習活動を重視することとした。本書は、その研究の成果を各教科の学習場面を事例を事例として取り上げつつ述べたものである。
-
言語活動を通して学習意欲を高める授業事例集
加藤圭司 他22名( 担当: 共編者(共編著者))
学事出版 2014年3月 ( ISBN:978-4-7619-2032-6 )
総ページ数:125 担当ページ:2-3 記述言語:日本語 著書種別:学術書
PISA型学力の育成について、中学校の実践レベルで取り組んでいる附属横浜中学校が、言語活動を重視する中で生み出される学習意欲について、各教科の具体的な学習場面を中心にその姿を分析・検討したものである。
学位論文 【 表示 / 非表示 】
-
文化的発達の視点からとらえる学習者の科学概念構築とその変容に関する研究
加藤圭司
2011年3月
未設定 単著 [査読有り]
-
学習者の岩石に関する学習経験と概念構造の形成の関係について
加藤圭司
1987年3月
学位論文(修士) 単著
論文 【 表示 / 非表示 】
-
科学的な探究の過程を内省する活動「科学の時間」がNOSの要素の理解に及ぼす効果について
中込 泰規, 加藤 圭司, 小倉 康
理科教育学研究 65 ( 2 ) 371 - 387 2024年11月 [査読有り]
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:一般社団法人 日本理科教育学会 共著
<p>本研究は,生徒が独自の視点から「科学の本質(Nature of Science,以下,NOSと略記)」の要素に関する考えを構築して,理解に導くことを重視した「科学の時間」を設定し,その実践の中で見られる生徒の思考過程に注目して,効果を事例的に検証したものである。科学の時間は,グループや学級での議論を中心として,科学的な探究の過程を内省することから,「探究を行う上で重要なこと」についてコンセンサスのとれた考えを創り出す活動である。科学の時間を通して,科学的な探究の過程を内省する視点を獲得し,その視点から,自他のNOSの要素に関する考えについて評価を行い,少しずつ考えを構築していく効果が見られた。生徒はより妥当な考えを創り出すために,①他者との議論や教師の手立てから,内省を行うための新たな視点を獲得し,②これまで用いていた視点との比較を行い,③どちらが内省を行う上で効果的な視点かを判断,決定して,④再び内省を実施する,一連の思考過程を辿っていた。科学の時間は,この思考を促すだけでなく,繰り返し生じさせる効果が見られた。さらに,科学的な探究の過程を繰り返し内省することや,生徒独自の視点からNOSの要素に関する考えを構築することに重点を置いた効果として,NOSの要素を柔軟に関連付けて,統合的な理解に導く効果も確認できた。</p>
-
科学的な探究から促される「科学の本質(NOS)」の理解の特徴に関する基礎的研究
中込泰規、加藤圭司、小倉康
臨床教科教育学会誌 25 ( 1 ) 65 - 80 2025年9月 [査読有り]
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 単著
-
科学的知識の統合・創発を支援する立体型イメージマップの開発と評価
中込 泰規, 加藤 圭司
理科教育学研究 64 ( 1 ) 13 - 26 2023年7月 [査読有り]
担当区分:最終著者, 責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:一般社団法人 日本理科教育学会 共著
<p>本研究は,二次元平面に展開する従前のイメージマップを拡張した立体型イメージマップを開発すると共に,生徒の主体的な課題解決を通した科学的知識の統合・創発にどのように寄与するかを明らかにすることを目的として,中込・加藤(2020)が明らかにした「俯瞰する行為」における思考過程と照らし合わせながら事例的分析を行なった。結果として,本研究で開発した立体型イメージマップを介して創り上げた抽象的な知識を基にして,異なる内容間を比較する視点の獲得と,具体的な知識から抽象的な知識を統合・創発しようとする思考が促されることが示唆された。また,同一単元内における異なる内容間の比較を通して,アブダクティブな思考が介在し,それにより抽象的な知識が少しずつ創り上げられていく可能性が示唆された。</p>
-
理科授業設計における「課題環境デザイン」の有効性の事例的検討 ~ ARCS動機づけモデルを基軸として ~
佐藤祐輔、中込泰規、加藤圭司
横浜国立大学教育学部紀要 I、教育科学 7 22 - 32 2024年1月
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:横浜国立大学教育学部 単著
-
対話を基軸とした中学校理科の問題解決過程における知識統合の実態
中込 泰規, 加藤 圭司
理科教育学研究 61 ( 3 ) 467 - 478 2021年3月 [査読有り]
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:一般社団法人 日本理科教育学会 共著
<p>本研究は,近年注目されている「深い学び」の実現に向けて,知識や技能を相互に関連づけて考え理解していくその思考過程の具体を明らかにすることを目的に,Linn(2000)の提唱する知識統合の理論を援用し,中学校理科における対話を基軸とした問題解決過程における生徒の思考の事例的分析を行った。結果として,生徒は,直近の問題を解決することを意図した「小さな統合(本研究では,これをMicro Integration:MIと称する)」を繰り返し生じさせる姿を見出すことができた。生徒は,問題解決に向けて「小さな統合」を通じて少しずつ知識や考えの抽象度を高め,その結果,科学的な知識や理論に到達していくという,知識統合が実現する実態を明らかにした。</p>
総説・解説記事等 【 表示 / 非表示 】
-
対話を通して子どもはどのように知識や考えを関連付けていくのか
中込泰規、加藤圭司
日本理科教育学会編「理科の教育」 71 ( 837 ) 46 - 47 2022年4月 [依頼有り]
担当区分:責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 単著
-
理科授業の変容とこれからの授業実践研究の課題 ―主体性・自律性が十分に発揮される学習過程の創造に向けて―
加藤圭司
日本理科教育学会編「理科の教育」 68 ( 608 ) 22 - 24 2019年9月
担当区分:筆頭著者 記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要) 出版者・発行元:東洋館出版社 単著
-
新しい教科書の使い方 ―よりよい授業づくりのために―(中学校)
鳩貝太郎,太田綾子,山下修一,松原静郎,宮内卓也,西出和彦,加藤圭司
公益財団法人 教科書研究センター 2023年8月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要) 単著
-
新しい教科書の使い方 ―よりよい授業づくりのために―(小学校)
鳩貝太郎,中村 潤,山下修一,松原静郎,宮内卓也,西出和彦,加藤圭司
公益財団法人 教科書研究センター 2022年10月
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要) 単著
-
新たな教育課題に対応する養成-研修一体型教師育成プログラムの試み
石田喜美,小水亮子,加藤圭司,大泉義一,泉真由子,梅澤秋久,和田一郎,杉山久仁子,鈴木允,島田広,鬼藤明仁,藤井佳世
日本教育大学協会研究年報( 第36集) 36 187 - 199 2018年1月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:日本教育大学協会 共著
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
知識統合理論をもとに「深い学び」を具現化する理科の授業デザインの実践的検討
2022年4月 - 2026年3月
基盤研究(C)
代表者:加藤圭司
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
-
科学的な探究の特徴から理科授業を省察する教師教育プログラムの開発に関する研究
2019年4月 - 2023年3月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
代表者:益田裕充
資金種別:競争的資金
-
学習者の科学を学ぶ意義の育成・変容に資する理科授業モデルの構築
2019年4月 - 2023年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
代表者:加藤圭司
資金種別:競争的資金
本研究は、2017年3月に告示された次期学習指導要領の小・中学校理科における重点項目の一つとして掲げられている、児童・生徒の「科学を学ぶ意義」の育成指針を明らかにすることを取り上げる。具体的には、児童・生徒の「科学を学ぶ意義」に関する意識の実態を、関連する要素・側面を措定する中で年齢横断的に解明するとともに、その特徴や傾向から先の意識が学校教育を通じて有意味に高まっていくための理科授業のデザイン原則を、実践の中から事例的に抽出することを試みる。そして、その抽出されたデザイン原則の妥当性を試行的な授業実践を通じて検証する中で、これからの小・中学校における理科学習指導において、「科学を学ぶ意義」を感得できる理科授業をモデル的に打ち立て、授業実践に寄与することを目指すものである。
-
学習者の科学観の構築と変容に資する授業実践要因の分析に関する臨床的研究
2015年4月 - 2018年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
代表者:加藤圭司
資金種別:競争的資金
-
学習者の科学観の構築と変容の要因に関する臨床的実践研究
2009年4月 - 2011年3月
科学研究費補助金 萌芽研究
代表者:加藤圭司
資金種別:競争的資金
その他競争的資金獲得・外部資金受入状況 【 表示 / 非表示 】
-
認知・非認知能力調査研究
2022年4月 - 2025年3月
地方自治体
代表者:加藤圭司
担当区分:研究代表者
横浜市学力・学習状況調査で測定されている非認知能力の4つの要素「メタ認知」「知的好奇心」「知的謙虚さ」「共感性」は,それぞれが効果的な学習を促進する基盤を成す重要な要素である。本研究では,これらの非認知能力と学力の相互関係を明らかにするとともに,児童生徒の非認知能力および学力を高めるための指導方法や指導方針を明らかにすることを目指すものである。
-
大学教員、大学生、小学校教員の3者連携における理科授業構築・実践プログラムの開発
2004年11月 - 2005年10月
民間財団等 理科・環境教育助成
代表者:加藤圭司
担当区分:研究代表者
研究発表 【 表示 / 非表示 】
-
思考の精緻化から見た理科授業の話合い活動における実態と課題
原田悠妃、有泉翔太、加藤圭司
日本理科教育学会第63回関東支部大会 2024年12月 日本理科教育学会関東支部
開催年月日: 2024年12月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:茨城大学
-
中学校理科の課題解決場面から見た生徒の批判的思考の実態
柳澤花香、熊谷卓行、加藤圭司
日本理科教育学会第63回関東支部大会 2024年12月 日本理科教育学会関東支部
開催年月日: 2024年12月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:茨城大学
-
小学生の条件制御における思考過程の実態と課題の分析
東郷修有、加藤圭司
日本理科教育学会第63回関東支部大会 2024年12月 日本理科教育学会関東支部
開催年月日: 2024年12月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:茨城大学
-
科学の本質(NOS)の構成要素の統合を促す学習活動の設定と効果
中込泰規、加藤圭司、小倉康
日本理科教育学会第74回全国大会 2024年9月 日本理科教育学会
開催年月日: 2024年9月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:龍谷大学
-
小・中学校理科の教科書の使い方に関する調査研究
松原静郎、宮内卓也、山下修二、西出和彦、加藤圭司、鳩貝太郎
日本理科教育学会第74回全国大会 2024年9月 日本理科教育学会
開催年月日: 2024年9月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:龍谷大学
学会誌・論文誌編集等 【 表示 / 非表示 】
-
理科教育学研究
編集委員
2017年7月-2021月8日 -
地学教育
「学会賞」「教育研究奨励賞」選定委員会委員
2008年6月-2009月5日 -
科学教育研究
編集委員(非常任)
2006年10月-2008月9日 -
日本理科教育学会誌「理科の教育」
編集委員
2005年-2007月3日 -
日本理科教育学会編「理科の教育」
編集委員
1999年4月-2002月3日
共同研究希望テーマ 【 表示 / 非表示 】
-
子どもの深い理解に寄与する小・中学校理科のカリキュラム開発に関する共同研究
-
子どもの深い理解を目指した小・中学校における理科授業構築と、それらの評価に関する研究
共同・受託研究情報 【 表示 / 非表示 】
-
認知・非認知能力調査研究
提供機関: 横浜市教育委員会 国内共同研究
研究期間: 2022年04月 - 2025年3月
-
子どもの科学的リテラシー向上を目指した義務教育9カ年の授業体系の開発
提供機関: 日産科学振興財団(現 日産財団) 企業等からの受託研究
研究期間: 2006年04月 - 2009年3月
担当授業科目(学内) 【 表示 / 非表示 】
-
2025年度 理科の高度教育研究方法論
大学院教育学研究科
-
2025年度 理科の授業デザイン論と実践
大学院教育学研究科
-
2025年度 人間社会と科学
大学院教育学研究科
-
2025年度 卒業研究
教育学部
-
2025年度 課題研究B(ゼミナール)
教育学部
担当経験のある授業科目(学外) 【 表示 / 非表示 】
-
理科教育法1
2004年4月 - 現在 機関名:日本女子大学
科目区分:その他
-
理科教育法Ⅲ
2003年1月 - 2007年9月 機関名:静岡大学
科目区分:その他
-
理科教育法Ⅲ
2001年8月 - 2001年9月 機関名:福岡教育大学
科目区分:学部専門科目
-
理科教育法1-2
1999年4月 - 現在 機関名:横浜市立大学
科目区分:その他
-
理科教育法1-1
1998年4月 - 現在 機関名:横浜市立大学
科目区分:その他
その他教育活動及び特記事項 【 表示 / 非表示 】
-
2024年12月思考の精緻化から見た理科授業の話合い活動における実態と課題 (学会等における学生の発表実績)
-
2024年12月中学校理科の課題解決場面から見た生徒の批判的思考の実態 (学会等における学生の発表実績)
-
2024年12月小学生の条件制御における思考過程の実態と課題の分析 (学会等における学生の発表実績)
-
2024年07月理科の実践研究の成果とその発展普及の視点 (教育方法・実践に関する発表、講演)
-
2024年06月-2025年01月自分の成長を実感できる授業とICTの活用 (教育方法・実践に関する発表、講演)
委員歴 【 表示 / 非表示 】
-
横浜市教育課程研究委員会(小・中学校理科)
2019年04月 - 現在 理科専門部会委員
委員区分:自治体
-
授業における教科書の使い方に関する調査研究委員会
2018年06月 - 2024年3月 理科部会委員
委員区分:学協会
-
「科学の甲子園」および「科学の甲子園ジュニア」推進委員会
2018年04月 - 現在 推進委員
委員区分:その他
-
神奈川県教育委員会 県立高等学校第三者評価
2016年04月 - 2024年3月 評価委員
委員区分:自治体
-
大和市教育委員会自己点検評価委員会
2015年04月 - 現在 外部有識者
委員区分:自治体
社会活動(公開講座等) 【 表示 / 非表示 】
-
第56回全国小学校理科研究協議会研究大会
役割:講師, 助言・指導
全国小学校理科研究協議会 2023年11月
-
鎌倉市教育委員会・教育センター夏季研修会
役割:講師, 助言・指導, 情報提供
鎌倉市教育センター 2023年8月
-
鎌倉市教育委員会・教育センター夏季研修会
役割:講師, 助言・指導
鎌倉市教育センター 鎌倉市教育委員会・教育センター夏季研修会 2022年8月
-
横浜市教育課程研究(理科)夏季研修会
役割:講師, 助言・指導
横販市教育委員会教育課程研究会(理科) 横浜市教育課程研究(理科)夏季研修会 2022年7月 - 現在
-
川崎市立下沼部小学校理科授業研究
役割:講師, 助言・指導
川崎市立下沼部小学校 2022年6月 - 2023年11月
学術貢献活動 【 表示 / 非表示 】
-
学力と社会情動的コンピテンシーの関係の解明に向けた教育データの活用可能性
役割:学術調査立案・実施
横浜国立大学教育学部 2023年3月
種別:大会・シンポジウム等
-
論文誌「理科教育学研究」編集
役割:査読
日本理科教育学会「理科教育学研究」編集委員会 2017年7月 - 2022年6月
種別:学会・研究会等
学内活動 【 表示 / 非表示 】
-
2024年04月-現在附属図書館長 (その他の主要活動)
-
2022年04月-2024年3月教育研究評議員 (全学委員会)
-
2020年04月-2024年3月教育学部副学部長 (その他の主要活動)
-
2018年09月-2019年5月教育組織改革WG メンバー (全学委員会)
-
2016年04月-2018年3月教育研究評議員・副学部長 (その他の主要活動)