|
Affiliation |
Faculty of Urban Innovation, Division of Urban Innovation |
|
Job Title |
Professor |
|
Date of Birth |
1968 |
|
Research Fields, Keywords |
思想・表現の考古学, 自然哲学、超都市理論 |
|
Mail Address |
|
|
YNU Research Center |
KURENUMA Norihisa
|
|
The Best Research Achievement in Research Career 【 display / non-display 】
-
【Book】 『都市は揺れている : 五つの対話』(東信堂) 2020.04
【Published Thesis】 Reassembling the 2024.03
【Published Thesis】 The Rise of the Cosmic in the 20th Century Culture: For Cosmic Machines and the Anthropocene's Wake 2018.03
The Best Research Achievement in the last 5 years 【 display / non-display 】
-
【Published Thesis】 Reassembling the 2024.03
【Published Thesis】 「下村寅太郎の哲学に向かう」(『常盤台人間文化論叢』) 2022.03
【Published Thesis】 REORIENT: Another Paradigm of Activity 2021.03
【Book】 『都市科学事典』(春風社) 2021.02
【Book】 暦でみる生物文化多様性 : 二十四節気・七十二候(横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ) 2024
YNU Research Center 【 display / non-display 】
Education 【 display / non-display 】
-
-1999
The University of Tokyo Doctor Course Accomplished credits for doctoral program
-
-1998
Graduate School, The University of Kent Communication and Image Studies Doctor Course Completed
-
-1990
The University of Tokyo History and Philosophy of Sciences Graduated
Degree 【 display / non-display 】
-
Master of Philosophy - Graduate School, The University of Kent
-
Master of Philosophy - The University of Tokyo
Campus Career 【 display / non-display 】
-
2014.4
Duty Yokohama National UniversityFaculty of Urban Innovation Division of Urban Innovation Professor
-
2011.4-2014.3
Duty Yokohama National UniversityFaculty of Urban Innovation Division of Urban Innovation Associate Professor
-
2007.4-2011.3
Duty Yokohama National UniversityCollege of Education and Human Sciences Associate Professor
-
2001.10-2007.3
Duty Yokohama National UniversityCollege of Education and Human Sciences Associate Professor
-
2023.4
Concurrently Yokohama National UniversityInstitute for Multidisciplinary Sciences Professor
External Career 【 display / non-display 】
-
2008.4
Tokyo University of the Arts Department of Inter Media Art Part-time lecturer
-
2018.4
-
2017.10
-
2013.4-2023.9
-
2013.4-2015.9
Research Areas 【 display / non-display 】
-
Humanities & Social Sciences / Aesthetics and art studies
-
Humanities & Social Sciences / History of thought
-
Humanities & Social Sciences / Philosophy and ethics
Research Career 【 display / non-display 】
-
自然哲学、超都市理論
Cooperative Research
Project Year: 2017.6 - 2030
-
日本近代思想史ー下村寅太郎を核に
Project Year: 2016.4 - 2025
-
ジェームズ・J・ギブソンと20世紀アメリカの視覚文化
Project Year: 2009.4 - 2011.3
Books 【 display / non-display 】
-
吉原 直樹, 榑沼 範久, 都市空間研究会( Role: Joint editor , 「都市のスケールとリズムについて」「現代世界の始まりのマッシュルーム」「イスラーム都市から考える」「地中海世界のヴェネツィア」「都市と世界を揺らす」「都市空間研究会について」)
東信堂 ( ISBN:9784798916361 )
Total pages:176 Language:Japanese Book type:Scholarly book
「「明日の世界」「明日の都市」を揺らがせる、明後日の方向を向いた、あの「明日の世界」「明日の都市」がありうる。都市を根底から揺らすのは巨大地震や巨大津波、そして放射性物質を含む廃棄物汚染、世界的感染症流行(パンデミック)、経済戦争、軍事戦争ばかりではないのだ。第一に、重要ながら人口は唯一の世界の条件、都市の条件ではない。人類だけが地球の存在ではないことがひとつ。そして、atom(原子)を分割できるように、規定のindividual(個人・個体・個物)も複数の振動する要素に分割することができる。限られた世界のなかで人口は増大しても、存在量や要素量は増大しているだろうか。それでいてindividualは複数の要素の波動に分離しつつ、他の要素の波動と遭遇、結合することで、寄生虫的存在との長引く闘いのなか、別の波動の同盟を生み出していく。多種(マルチスピーシーズ)都市学、多種(マルチスピーシーズ)政治学。第二に、衰退の大波のなかにも多数の異質の小さい波動がうねり合い、蠢(うごめ)き合い、鳴り響いている。ことに現代世界では世界史の律動の尺度にねじれも生じている(われわれはブローデルの枠組みを変形する必要がある)。長期持続・大域延長に分類されるはずの環境が中期的・地域的に変動するかと思えば、短期・局所の社会的事件が長期持続・大域延長の環境を不可逆に変動させることもあるからだ。これは可能性の条件でもある。時間的にも空間的にも、小さなものが大きなものに包囲されるモデルだけで考える必要はない。だから、「明日の世界について、何か予言することなどとうてい不可能です」という言葉は、文字通りに受け止めなければならない。何よりもわれわれにとっては、「明日の世界」「明日の都市」が「私の属する世界」であり、「私の愛する世界」なのだから。」
-
『都市科学事典』
榑沼範久( Role: Contributor , 「地図のある歴史ー都市科学者と世界史的空間」「非都市のエレメンツーこの惑星を構成するものたち、そして水の法」)
春風社 ( ISBN:9784861107344 )
Total pages:1026 Responsible for pages:172-3, 988-9 Language:Japanese Book type:Dictionary, encyclopedia
「都市科学者は世界史を旅する。なぜなら、ひとつの国家のなかに都市があるのではなく、ひとつひとつの都市のなかにも、交差し、混合し、明滅する複数の国家や社会や文化があるからだ。何よりも都市は収集体(アッサンブラージュ)として在立する。そのため、歴史の時間のなかを過ぎ去っていったはずの出来事が、事象の混在する都市空間に痕跡をとどめ、世界史的出来事を表出してくることがある。だから都市科学者は、都市に碇泊することで世界史を旅するのだ。」(「地図のある歴史ー都市科学者と世界史的空間」)「われわれの名前を人間はまだ確定していない。いまだ都市と呼ばれるものに似た仲間もいるが、われわれは自然を超えるのみならず、都市を超えるものに変容しつつある。」(「非都市のエレメンツーこの惑星を構成するものたち、そして水の法」 )
-
『美学の事典』
榑沼範久( Role: Contributor , 「ポストメディウム/ポストメディア―現代芸術の条件としての」「芸術とポストモダニズム―範例としての『浜辺のアインシュタイン』」)
丸善 ( ISBN:9784621305423 )
Total pages:735 Responsible for pages:318-9, 346-7 Language:Japanese Book type:Dictionary, encyclopedia
グリーンバーグは「文化の危機に抵抗するモダニズムの条件を作品の物質性―グリーンバーグにとってのメディウム―の抵抗に置き, メディウムの抵抗との緊迫した関係に作品の魅力を感じ取っていった. (…)こうしたモダニズムの条件を, 実のところグリーンバーグは唯一の批評基準とみなしてはいない. 同時代でも, 歴史の展開に応じても, 他の批評基準が存在しうると注意を促していた.」(「ポストメディウム/ポストメディア―現代芸術の条件としての」 )「この非-オペラは, オーウェンスが論じた美学の水準のみならず, 世界の歴史の水準で把握することもできる。架空の歴史裁判で証言をすることもなく, 無言のままヴァイオリンを弾いている「アインシュタイン」を, 消費社会的な「歴史感覚の喪失」と診断することもできるが, 「正当化のメタ物語」に支えられた科学の末路(原子爆弾という歴史の悪夢)から「アインシュタイン」を離脱させ, 波打つリズムと「宇宙機械」に接近させる思考実験や操作と見ることもできるのだ.(…)科学-国家-経済の近代的三位一体から科学を切断し, 芸術との結合を促進させるような世界史の再発明も, この非-オペラは宿している.」(「芸術とポストモダニズム―範例としての『浜辺のアインシュタイン』」)
-
『運動+(反)成長-身体医文化論II』(武藤浩史・榑沼範久編)
武藤浩史(慶應義塾大学)他( Role: Joint author)
慶應義塾大学出版会
Language:Japanese Book type:Scholarly book
-
横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ, 河内 啓成, 倉田 薫子, 榑沼 範久 , 佐藤 峰, 鈴木 香織, 高芝 麻子 , 原口 健一 , 森部 絢嗣( Role: Sole author)
横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ
Language:Japanese Book type:Scholarly book
二十四節気・七十二候の暦から、生物・事物・文化・社会の絡まり合いを説き直す。【七十二候】紅花栄:「色の伝播と変容。蚕食桑と紅花栄の隣接。古代に大陸や大海を進んだ紅の道。花は黄から紅へとわたり、花餅は夜を跨いで純白の絹糸を真紅に染める。眉掃きをおもかげにして紅粉の花、行く末は誰が肌ふれん紅の花(芭蕉)に高畑勲監督『おもひでぽろぽろ』。紅花が引きこむ過去と未来の幻想。」、【二十四節気】冬至:「二つの世界ではやはりそれぞれ二つの別の自分があるのではないか」。寺田寅彦がそう書いたのは「東京の自分」と「星野の自分」の来復のことだ(『柿の種』)。冬至に星野温泉の柚子湯につかり物思いに耽る。夏至が遠い別の世界にある気がする。「冬の自分」と「夏の自分」もあるのではないか。」など。
Thesis for a degree 【 display / non-display 】
-
The Male Look and Its Vicissitude: A Study through Visual Representations, Feminism, and Psychoanalysis
1998.10
No Setting Single Work [Reviewed]
-
マルセル・デュシャン《階段を降りる裸体[No.2]》における“運動の問題”
榑沼範久
1993.3
No Setting Single Work [Reviewed]
イタリア未来派や映画前史(マレーやマイブリッチの高速度写真撮影)からの影響をもとに、絵画における運動の表象として語られてきたデュシャンの絵画《階段を降りる裸体[No.2]》は、運動の問題における混合物である。作品の細部を観察してみるならば、この絵画は運動を表象すると同時に、運動を解体して「遅延」を導入する「反時代的」作品であることが判明する。この見解をデュシャンのメモの読解からも支える論考。
Papers 【 display / non-display 】
-
Reassembling the Machine Montage: Spinoza, Hobbes, and Höch
Norihisa KURENUMA
The Journal of Human and Cultural Sciences (The Society for the Human and Cultural Sciences in Musashi University) 55 ( 2 ) 159 - 171 2024.3 [Invited]
Authorship:Lead author, Last author, Corresponding author Language:Japanese Publishing type:Research paper (bulletin of university, research institution) Single Work
-
榑沼範久
『常盤台人間文化論叢』 6 ( 1 ) 145 - 158 2020.3
Language:Japanese Publishing type:Research paper (bulletin of university, research institution) Publisher:横浜国立大学大学院都市イノベーション学府・研究院 Single Work
「われわれは海の道—「海上の道」(柳田国男)とはまた別の次元にある海の道—、そして海坂が閉じられた世界に生きている、ということだ。では、いつまでも海の道をとおって通い来る海神の姫の願いを叶えることは、もはやできないのだろうか。海の道が、海坂が閉じられた世界のなかで、海神の姫の願いを聞き届け、その願いを叶えようとするのが、われわれの世界における芸術の使命のひとつではないか。」
「『古事記』では、人間と動物に共通する起源は人間性ではない。それは神代に記録されている人神性なのである。動物が元-人間なのではなく、動物も人間もひとしく元-人神だった。文字通り豊玉姫や山幸彦のような人神だった。その意味で、この国は人間が不在の無人島だった。人間と動物に共通する原初的な条件とは、動物性のことではなく、人間性のことでもなく、人神性なのである。おそらく人間もまた、自らと同じままであり続けた者ではない。」
「大いなる分割によって、人間と動物がともに人神性をいかに失ったのか。この超自然的出来事と、海と陸を行き通うことができたはずの元-人神のありかを、『古事記』は地政的な覇権争いの彼方に物語っている。超自然的な人神たちが渚で夢を混ぜ合わせることができたはずの、社会契約を超えた超自然契約の神話として。人神性からすれば、海坂が閉じられたあとの世界のほうが悪い夢であり、海の道を通い来る願いこそ現実なのだ。われわれは「人新世」以後の地球の新しい法(ノモス)を探るとき、こうした神話に含まれる「貴重な真実」を見る。」 -
2000: Bonnard, or A Pictorial Space Odyssey
2018.9 [Invited]
Language:Japanese Publishing type:Research paper (other science council materials etc.) Single Work
-
The Rise of the Cosmic in the 20th Century Culture: For Cosmic Machines and the Anthropocene's Wake
KURENUMA Norihisa
Tokiwadai journal of human sciences 4 ( 1 ) 65 - 88 2018.3 [Reviewed]
Language:Japanese Publishing type:Research paper (bulletin of university, research institution) Publisher:Yokohama National University,Faculty of Urban Innovation Single Work
-
「生態学的建築をめざして―建築とギブソンの生態学」
榑沼 範久
『思想』 ( 1045 ) 77 - 107 2011.5
Language:Japanese Publishing type:Research paper (scientific journal) Publisher:岩波書店 Single Work
Review Papers 【 display / non-display 】
-
Deciphering human possibilities: Looking toward what comes after urbanization
Norihisa KURENUMA
( Vol. 12 ) 24 - 35 2023.3
Language:Japanese Publishing type:Article, review, commentary, editorial, etc. (other) Single Work
-
Feed the flame: The Genealogy of Hitoshi Kuriyama
Hotoshi Kuriyama, NOTHINGNESS IS FULLNESS, FULLNESS IS NOTHINGNESS 40 - 43 2023.12
Language:Japanese Publishing type:Article, review, commentary, editorial, etc. (other) Single Work
-
"On representation and modeling of the ground"
Mamoru KIKUMOTO and Norihisa KURENUMA
2022.3
Language:Japanese Publishing type:Other Single Work
-
Artistic Experimental Life on a Dark Planet: Hitoshi Kuriyama, Something Comes from Nothing
Kurenuma Norihisa
2019.12
Language:Japanese Publishing type:Article, review, commentary, editorial, etc. (other) Publisher:ART FRONT GALLERY Single Work
Other Link: https://www.artfrontgallery.com/exhibition/archive/2019_10/3956.html
-
榑沼範久
10+1 website 2017.8
Language:Japanese Publishing type:Article, review, commentary, editorial, etc. (trade magazine, newspaper, online media) Single Work
Works 【 display / non-display 】
-
地球と建築2
石上純也、榑沼範久
2012.1
Work type:Other
-
地球と建築1
平田晃久、藤本壮介、榑沼範久
2012.1
Work type:Other
-
三上晴子 欲望のコード|アーティスト・トーク
三上晴子、池上高志、榑沼範久、畠中実
2011.12
Work type:Other
-
これから生まれる建築と生態のために2
平田晃久、榑沼範久
2010.12
Work type:Other Location:北仲スクール/ヨコハマ創造都市センター
-
これから生まれる建築と生態のために
藤本壮介、榑沼範久
2010.10
Work type:Other Location:北仲スクール/ヨコハマ創造都市センター
Awards 【 display / non-display 】
Grant-in-Aid for Scientific Research 【 display / non-display 】
-
下村寅太郎の「潜在的著作」を集成する
2020.4 - 2026.3
科学研究費補助金 Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Investigator(s):榑沼範久
Grant type:Competitive
京都学派の著名な哲学者である下村寅太郎(1902-1995)は、1973年の定年退職後も著述活動とは別に、自身の研究談話会「プリムツァール会」で広大な思索を録音テープに残していた。「真の著作遍歴は著作以外にあるとすらいえる」、「テープの存するかぎり潜在的著作と称してもよいであろう」とは下村自身の言である。だが、『下村寅太郎著作集』(1988-1999)の完結から20年以上が過ぎた現在でも、この「潜在的著作」は公刊されていない。録音された音声を文字化し、選択・校閲・編集を経て刊行を目指す本研究は、下村の未知の側面の発見にとどまらず、日本近代思想史の研究にとっても重要な学術資料の集成になるだろう。
-
戦争と芸術論
2004.4 - 2005.3
科学研究費補助金 Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Investigator(s):木下長宏
Grant type:Competitive
「戦争」は人類の歴史を貫通する重大事であり、つねに最も根源的な社会変容の契機となり、その結果でもあり、人間性に関わる出来事として、人間の生活・思索活動に多大な影響を与えてきた。「芸術活動」ももちろんその例外ではない。従来、芸術史・芸術論の分野では、限られた時点での戦争と芸術表現に関する個別的な研究(例えば、「第二次世界大戦における戦争画の研究」、「翼産体制下の文学」など)は深められてきたが、われわれはそうした個別研究の成果・蓄積を踏まえて、「戦争」という人類にとって不可避とも言うべき行動を、広く地球上に見わたし、近代から現代という時代において、その行動が芸術と呼ばれる領域のなかで、どのように受け取られ、また社会へ返されていったかを「思想」のありかたとして追及して行こうとしている。戦争と「芸術論」と敢えて題したのは、そのような意味での広義の思想的活動に焦点を絞ろうとしたからである。いいかえれば、結果としての作品(海外、映像、詩、小説、音楽など)にではなく、そうした作品が作られ、それが享受され後世に受け継がれていく過程総体のなかで、「戦争」との関わりを解き明かそうとするものである。
Presentations 【 display / non-display 】
-
下村寅太郎の「潜在的著作」―プリムツァール会の録音テープについて
榑沼 範久 [Invited]
日本哲学史フォーラム 2024.10 京都大学文学研究科日本哲学史専修
Event date: 2024.10
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
Venue:京都大学
-
小宮山恵三郎氏インタビュー「下村寅太郎の記憶―よみがえる哲学者の声とその近辺」
小宮山恵三郎、上原麻有子(インタビュアー)、榑沼範久(インタビュアー) [Invited]
日本哲学史フォーラム 2024.10 京都大学文学研究科日本哲学史専修
Event date: 2024.10
Language:Japanese Presentation type:Other
Venue:京都大学
-
青木繁《海の幸》(1904[明治37]年)を考える
榑沼 範久
生物文化多様性ラボセミナー 2024.11 横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ
Event date: 2024.11
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
Venue:横浜国立大学
-
「われわれはみな地衣類」なのだろうか?
榑沼 範久
生物文化多様性ラボセミナー 2024.5 横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ
Event date: 2024.5
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
Venue:横浜国立大学
-
榑沼 範久 [Invited]
地衣類研究会オンライン地衣類講座 2024.4 地衣類研究会
Event date: 2024.4
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (invited, special)
Venue:オンライン(Zoom)
都市の現在と未来を考える授業で、『廃墟のロビンソン』(パトリック・キーラー監督、2010)という英国の映画を観ていたときのことです。道路標識に付着する地衣類がくりかえし映し出されていました。翌月には地衣類研究会入会申込書を送りました。2022年の8月のことです。過去に自分はダーウィンに関する文章を書いたことがあるにしても、なぜこれほど地衣類に惹かれたのか。(人文学者の私が)地衣類に関心を抱く理由を話してみたいと思います。ただし、地衣類に共生の理想を投影するのではなく。地衣類に「共生」「他利」「抵抗」「美醜」を見るよりむしろ表面性、断片性、不定形、(生態系全体にとっての)”無用性”を積極的に認識する必要を感じています。地衣類は例えば菌根や菌糸のネットワークと異なり、森の生態系に寄与するわけではなく、付着した樹木と共生関係を結ぶわけでも、寄生関係を結ぶわけでもなく、樹皮であろうとコンクリートであろうと金属製の人工物であろうと無関係に、ただ付着しています。自然/生態系/ガイア全体の一部でなく、そこからただ外れた生命のありかたとして見ること、惑星生物学の対象としての生物であると提唱したいのです。『生態進化発生学: エコ-エボ-デボの夜明け』の著者の一人、スコット・F・ギルバートは共著論文(Scott F. Gilbert, Jan Sapp and Alfred I. Tauber, “A Symbiotic View of Life: We Have Never Been Individuals,” 2012)の最後を“We are all lichens(われわれはみな地衣類である)”と結んでいます。しかし、個体内外における生物的共生の全体のなかに地衣類を代表者として還元するのは、前述した地衣類の特徴を消去することになるのではないでしょうか。自然/生態系/ガイア全体の一部でなく、そこからただ外れた生命のありかた。これが例外ではない生命の概念にわたしたちが到達したとしたら、そのときこそ“We are all lichens(われわれはみな地衣類である)”と言うことができるはずです。
Preferred joint research theme 【 display / non-display 】
-
都市理論
-
日本思想史
-
近現代芸術研究
-
進化論
Past of Collaboration and Commissioned Research 【 display / non-display 】
-
戦争と芸術論
Cooperative Research within Japan
Project Year: 2004.4 - 2006.3
Charge of on-campus class subject 【 display / non-display 】
-
2025 Art and Culture Studio A2
College of Urban Sciences
-
2025 Art and Culture Studio A1
College of Urban Sciences
-
2025 Aesthetics of Space
College of Urban Sciences
-
2025 Lesture on Space and Culture
College of Urban Sciences
-
2025 Seminar on the Aesthetics of Space 2(English)
College of Urban Sciences
Charge of off-campus class subject 【 display / non-display 】
-
メディア概論
2008.4 Institution:東京藝術大学
-
芸術学C
2018.4 Institution:慶應義塾大学
-
今、都市を考える
2022.10 Institution:放送大学
この地球という惑星に誕生したサピエンスの歴史のなかで、都市とは果たして何だったのでしょう か。今、都市はどうなっているのでしょうか。そして都市の未来はどうなっていくのでしょうか。どうな る必要があるのでしょうか。都市は自由の場所でしょうか。孤独と病の源泉でしょうか。欲望と富の 集積地でしょうか。文化と文明の発信地でしょうか。攻撃や防衛の対象でしょうか。環境の最大の 破壊者でしょうか。都市はサピエンスだけのものでしょうか。こうした問いを立てながら、今、都市に ついて考えるべきことを探っていきたいと思います。
第1回 自分史のなかの都市を語る
第2回 今、都市をめぐり話し合う
第3回 「祝祭都市の政治」から展開する
第4回 「揺らぐ都市へ/から」「都市という謎にせまる」から展開する
第5回 「ユートピアかディストピアか」から展開する
第6回 「都市のスケールとリズムについて」から展開する
第7回 「イスラーム都市から考える」から展開する
第8回 「都市と世界を揺らす」から展開する
(教科書:『都市は揺れているー五つの対話』(吉原直樹・榑沼範久/都市空間研究会編、東信堂、2020年) -
<世界史>を改めて考える
2021.12 Institution:放送大学
-
テクノロジー文化論
2013.4 - 2023.9 Institution:武蔵大学
Committee Memberships 【 display / non-display 】
-
横浜市芸術文化財団
2012.4 - 2014.3 先駆的芸術活動審査委員
Committee type:Other
Social Contribution(Extension lecture) 【 display / non-display 】
-
山森裕毅『フェリックス・ガタリの哲学』合評会
Role(s): Guest, Logistic support
DGラボ 山森裕毅『フェリックス・ガタリの哲学』合評会 横浜国立大学都市科学部講義棟103 2025.3
Audience: University students, Teachers, Researchers, General public
Type:Planning and holding meetings,conferences,e.t.c.
-
講義「海と陸をつなぐ道〜『古事記』から出発して〜」
Role(s): Lecturer
東京都立新宿高等学校 東京都立新宿高等学校出張講義 2024.10
-
日建設計PYNT×横浜国立大学「まちづくり:未来の"境界"をさぐる」(全4回)
Role(s): Commentator, Host, Planner
横浜国立大学総合学術高等研究院豊穣な社会研究センター、日建設計PYNT 「まちづくり:未来の"境界"をさぐる」 2024.9 - 2025.3
-
STRUGGLE FOR PARADISE/ LIFE IN DISASTER: "This could be heaven or this could be hell"
Role(s): Panelist, Host, Edit
2023.9
-
THINKING ABOUT SOCIAL WELL-BEING IN THE FUTURE THROUGH DISASTER
Role(s): Guest, Host, Edit
2023.9
Media Coverage 【 display / non-display 】
-
OTTAVA「今夜もウェルネス!」#72 出演
OTTAVA 今夜もウェルネス! 2021.5
最晩年(50代半ば)のルートヴィヒ・ファン・ベートーヴェン(1770-1827)が『交響曲第9番』(1824年)のあとに集中して取り組んだ弦楽四重奏曲、そのなかでも亡くなる前の年(1826年)に完成させた2曲を取り上げる。フランツ・シューベルト(1797-1828)、物理学者ロバート・オッペンハイマー(1904-1967)、そしてミラン・クンデラの小説『存在の耐えられない軽さ』(1984)も話に交差させながら聴く曲は、ベートーヴェン「弦楽四重奏曲 第14番」(作品131)、「弦楽四重奏曲 第16番」(作品135)から。
-
OTTAVA「今夜もウェルネス!」#64 出演
OTTAVA 今夜もウェルネス! 2020.3
不確実に揺れ動く社会と世界のなかで、さまざまな人生の嵐や病と向き合いながら、まだ聴こえない音楽を追究していくロベルト・シューマン(1810-1856)について語る。取り上げる曲は、オーボエとピアノのための「3つのロマンス」Op.94(1849)、ホルンのための「アダージョとアレグロ」Op.70(1849)、「チェロ協奏曲」Op.129(1850)など。
-
OTTAVA「今夜もウェルネス!」#61 出演
OTTAVA 今夜もウェルネス! 2020.2
グスタフ・マーラー作曲、交響曲第9番(1909)、第4楽章アダージョ(緩徐楽章)の聴きどころと、なぜマーラーの楽曲がいまだ私たちにリアルに響くのか、その歴史的・社会的な意味を中心に語る。
-
OTTAVA「今夜もウェルネス!」#60 出演
OTTAVA 今夜もウェルネス! 2020.2
グスタフ・マーラー作曲『大地の歌』(1908)の聴きどころと、科学と芸術を横断するその楽曲の文化史的位相を中心に語る。
-
東京藝術大学 先端○展 公開講評会
東京藝術大学先端芸術表現科 東京藝術大学上野校地 絵画棟1階 アートスペース 2016.12
東京藝術大学先端芸術表現科1年生の展覧会(先端◯展)の最終日に開催された公開の作品講評会・講評者。

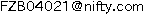


 ORCID
ORCID