|
所属組織 |
大学院都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 |
|
職名 |
教授 |
|
生年 |
1968年 |
|
研究キーワード |
思想・表現の考古学、自然哲学、超都市理論 |
|
メールアドレス |
|
|
YNU研究拠点 |
榑沼 範久 (クレヌマ ノリヒサ)
KURENUMA Norihisa
|
|
代表的な業績 【 表示 / 非表示 】
-
【著書】 『都市は揺れている : 五つの対話』(東信堂) 2020年04月
【論文】 「〈機械〉をモンタージュ(組み立て)しなおす—スピノザ・ホッブズ・ヘーヒ」(『人文学会雑誌』(武蔵大学人文学会)) 2024年03月
【論文】 20世紀の文化における宇宙的なものの上昇─宇宙機械と人新世の通夜=覚醒のために 2018年03月
直近の代表的な業績 (過去5年) 【 表示 / 非表示 】
-
【論文】 「〈機械〉をモンタージュ(組み立て)しなおす——スピノザ・ホッブズ・ヘーヒ」(『人文学会雑誌』(武蔵大学人文学会)) 2024年03月
【論文】 「下村寅太郎の哲学に向かう」(『常盤台人間文化論叢』) 2022年03月
【論文】 「リオリエントー活動性のアナザー・パラダイム」(『常盤台人間文化論叢』) 2021年03月
【著書】 『都市科学事典』(春風社) 2021年02月
【著書】 暦でみる生物文化多様性 : 二十四節気・七十二候(横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ) 2024年
プロフィール 【 表示 / 非表示 】
-
表象文化論専攻. 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院/都市科学部教授. 1968年生. 英国ケント大学大学院MPhil課程修了、東京大学総合文化研究科博士課程単位取得退学. MPhil(人文学).〈著作〉:「20世紀の文化における宇宙的なものの上昇――宇宙機械と人新世の通夜=覚醒のために」(『常盤台人間文化論叢』第4巻、横浜国立大学都市イノベーション研究院、2018年);「2000年—ボナール、絵画空間の冒険(2000: Bonnard, or A Pictorial Space Odyssey)」(『ピエール・ボナール展 Pierre Bonnard: l’éternel été』オルセー美術館特別企画、国立新美術館、日本経済新聞社、2018年);「海神の姫から見た世界――海道、人神性、超自然契約」(『常盤台人間文化論叢』第6巻、2020年)など.
学歴 【 表示 / 非表示 】
-
-1999年
東京大学 総合文化研究科 超域文化科学専攻(表象文化論) 博士課程 単位取得満期退学
-
-1998年
英国ケント大学大学院 人文科学研究科 コミュニケーション・映像研究 博士課程 修了
-
-1990年
東京大学 教養学部 科学史・科学哲学 卒業
学内所属歴 【 表示 / 非表示 】
-
2014年4月-現在
専任 横浜国立大学 大学院都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 教授
-
2011年4月-2014年3月
専任 横浜国立大学 大学院都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 准教授
-
2007年4月-2011年3月
専任 横浜国立大学 教育人間科学部 准教授
-
2001年10月-2007年3月
専任 横浜国立大学 教育人間科学部 助教授
-
2023年4月-現在
併任 横浜国立大学 総合学術高等研究院 教授
学外略歴 【 表示 / 非表示 】
-
2008年4月-現在
東京藝術大学 美術学部先端芸術表現科 非常勤講師
-
2018年4月-現在
慶應義塾大学 文学部 非常勤講師
-
2017年10月-現在
放送大学 神奈川学習センター 面接講師
-
2013年4月-2023年9月
武蔵大学 人文学部 非常勤講師
-
2013年4月-2015年9月
東京大学 教養学部教養学科 非常勤講師
研究経歴 【 表示 / 非表示 】
-
自然哲学、超都市理論
共同研究
研究期間: 2017年6月 - 2030年
-
日本近代思想史ー下村寅太郎を核に
研究期間: 2016年4月 - 2025年
-
ジェームズ・J・ギブソンと20世紀アメリカの視覚文化
研究期間: 2009年4月 - 2011年3月
著書 【 表示 / 非表示 】
-
吉原 直樹, 榑沼 範久, 都市空間研究会( 担当: 共編者(共編著者) , 範囲: 「都市のスケールとリズムについて」「現代世界の始まりのマッシュルーム」「イスラーム都市から考える」「地中海世界のヴェネツィア」「都市と世界を揺らす」「都市空間研究会について」)
東信堂 2020年4月 ( ISBN:9784798916361 )
総ページ数:176 記述言語:日本語 著書種別:学術書
「「明日の世界」「明日の都市」を揺らがせる、明後日の方向を向いた、あの「明日の世界」「明日の都市」がありうる。都市を根底から揺らすのは巨大地震や巨大津波、そして放射性物質を含む廃棄物汚染、世界的感染症流行(パンデミック)、経済戦争、軍事戦争ばかりではないのだ。第一に、重要ながら人口は唯一の世界の条件、都市の条件ではない。人類だけが地球の存在ではないことがひとつ。そして、atom(原子)を分割できるように、規定のindividual(個人・個体・個物)も複数の振動する要素に分割することができる。限られた世界のなかで人口は増大しても、存在量や要素量は増大しているだろうか。それでいてindividualは複数の要素の波動に分離しつつ、他の要素の波動と遭遇、結合することで、寄生虫的存在との長引く闘いのなか、別の波動の同盟を生み出していく。多種(マルチスピーシーズ)都市学、多種(マルチスピーシーズ)政治学。第二に、衰退の大波のなかにも多数の異質の小さい波動がうねり合い、蠢(うごめ)き合い、鳴り響いている。ことに現代世界では世界史の律動の尺度にねじれも生じている(われわれはブローデルの枠組みを変形する必要がある)。長期持続・大域延長に分類されるはずの環境が中期的・地域的に変動するかと思えば、短期・局所の社会的事件が長期持続・大域延長の環境を不可逆に変動させることもあるからだ。これは可能性の条件でもある。時間的にも空間的にも、小さなものが大きなものに包囲されるモデルだけで考える必要はない。だから、「明日の世界について、何か予言することなどとうてい不可能です」という言葉は、文字通りに受け止めなければならない。何よりもわれわれにとっては、「明日の世界」「明日の都市」が「私の属する世界」であり、「私の愛する世界」なのだから。」
-
『都市科学事典』
榑沼範久( 担当: 分担執筆 , 範囲: 「地図のある歴史ー都市科学者と世界史的空間」「非都市のエレメンツーこの惑星を構成するものたち、そして水の法」)
春風社 2021年2月 ( ISBN:9784861107344 )
総ページ数:1026 担当ページ:172-3, 988-9 記述言語:日本語 著書種別:事典・辞書
「都市科学者は世界史を旅する。なぜなら、ひとつの国家のなかに都市があるのではなく、ひとつひとつの都市のなかにも、交差し、混合し、明滅する複数の国家や社会や文化があるからだ。何よりも都市は収集体(アッサンブラージュ)として在立する。そのため、歴史の時間のなかを過ぎ去っていったはずの出来事が、事象の混在する都市空間に痕跡をとどめ、世界史的出来事を表出してくることがある。だから都市科学者は、都市に碇泊することで世界史を旅するのだ。」(「地図のある歴史ー都市科学者と世界史的空間」)「われわれの名前を人間はまだ確定していない。いまだ都市と呼ばれるものに似た仲間もいるが、われわれは自然を超えるのみならず、都市を超えるものに変容しつつある。」(「非都市のエレメンツーこの惑星を構成するものたち、そして水の法」 )
-
『美学の事典』
榑沼範久( 担当: 分担執筆 , 範囲: 「ポストメディウム/ポストメディア―現代芸術の条件としての」「芸術とポストモダニズム―範例としての『浜辺のアインシュタイン』」)
丸善 2020年12月 ( ISBN:9784621305423 )
総ページ数:735 担当ページ:318-9, 346-7 記述言語:日本語 著書種別:事典・辞書
グリーンバーグは「文化の危機に抵抗するモダニズムの条件を作品の物質性―グリーンバーグにとってのメディウム―の抵抗に置き, メディウムの抵抗との緊迫した関係に作品の魅力を感じ取っていった. (…)こうしたモダニズムの条件を, 実のところグリーンバーグは唯一の批評基準とみなしてはいない. 同時代でも, 歴史の展開に応じても, 他の批評基準が存在しうると注意を促していた.」(「ポストメディウム/ポストメディア―現代芸術の条件としての」 )「この非-オペラは, オーウェンスが論じた美学の水準のみならず, 世界の歴史の水準で把握することもできる。架空の歴史裁判で証言をすることもなく, 無言のままヴァイオリンを弾いている「アインシュタイン」を, 消費社会的な「歴史感覚の喪失」と診断することもできるが, 「正当化のメタ物語」に支えられた科学の末路(原子爆弾という歴史の悪夢)から「アインシュタイン」を離脱させ, 波打つリズムと「宇宙機械」に接近させる思考実験や操作と見ることもできるのだ.(…)科学-国家-経済の近代的三位一体から科学を切断し, 芸術との結合を促進させるような世界史の再発明も, この非-オペラは宿している.」(「芸術とポストモダニズム―範例としての『浜辺のアインシュタイン』」)
-
『運動+(反)成長-身体医文化論II』(武藤浩史・榑沼範久編)
武藤浩史(慶應義塾大学)他( 担当: 共著)
慶應義塾大学出版会 2003年
記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ, 河内 啓成, 倉田 薫子, 榑沼 範久 , 佐藤 峰, 鈴木 香織, 高芝 麻子 , 原口 健一 , 森部 絢嗣( 担当: 単著)
横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ 2024年8月
記述言語:日本語 著書種別:学術書
二十四節気・七十二候の暦から、生物・事物・文化・社会の絡まり合いを説き直す。【七十二候】紅花栄:「色の伝播と変容。蚕食桑と紅花栄の隣接。古代に大陸や大海を進んだ紅の道。花は黄から紅へとわたり、花餅は夜を跨いで純白の絹糸を真紅に染める。眉掃きをおもかげにして紅粉の花、行く末は誰が肌ふれん紅の花(芭蕉)に高畑勲監督『おもひでぽろぽろ』。紅花が引きこむ過去と未来の幻想。」、【二十四節気】冬至:「二つの世界ではやはりそれぞれ二つの別の自分があるのではないか」。寺田寅彦がそう書いたのは「東京の自分」と「星野の自分」の来復のことだ(『柿の種』)。冬至に星野温泉の柚子湯につかり物思いに耽る。夏至が遠い別の世界にある気がする。「冬の自分」と「夏の自分」もあるのではないか。」など。
学位論文 【 表示 / 非表示 】
-
男性的眼差しとその運命―視覚表象、フェミニズム、精神分析
榑沼範久
1998年10月
未設定 単著 [査読有り]
「男の眼差し」はフェミニズム理論を中心に、「女の肉体」に及ぼす支配性を問題視され、批判の焦点になってきた。本学位論文は、フェミニズム理論も素材としてきた絵画・写真・映画(とくにヒッチコックの諸作品やパウエル監督《ピーピング・トム》)の細部を観察し直すとともに、フェミニズム理論を支えていたフロイトとラカンの精神分析理論を、その特異な「視覚欲動」の概念に注目することによって、「男の眼差し」を根源的受動性として見出した。
-
マルセル・デュシャン《階段を降りる裸体[No.2]》における“運動の問題”
榑沼範久
1993年3月
未設定 単著 [査読有り]
イタリア未来派や映画前史(マレーやマイブリッチの高速度写真撮影)からの影響をもとに、絵画における運動の表象として語られてきたデュシャンの絵画《階段を降りる裸体[No.2]》は、運動の問題における混合物である。作品の細部を観察してみるならば、この絵画は運動を表象すると同時に、運動を解体して「遅延」を導入する「反時代的」作品であることが判明する。この見解をデュシャンのメモの読解からも支える論考。
論文 【 表示 / 非表示 】
-
「〈機械〉をモンタージュ(組み立て)しなおす—スピノザ・ホッブズ・ヘーヒ」
榑沼範久
『人文学会雑誌』(武蔵大学人文学会) 55 ( 2 ) 159 - 171 2024年3月 [招待有り]
担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要) 単著
武蔵大学人文学会『人文学会雑誌』第55巻 第2号(香川檀教授記念号)への招待論文。第1節:「人間の隷属」とその彼岸、第2節:リヴァイアサンのモンタージュ(組み立て)にハサミを入れる、第3節:モンタージュ(組み立て)の方向転換の三節構成。なぜ「われわれは身体のなしうることさえも知らない」のか。なぜ「われわれは自分たちがいかなる変様をうけいれることができるのかということさえ知らないし、またわれわれの力がどこまで達するかも知らない」のか。ドゥルーズ/スピノザのこうした問いは、ホッブズ『リヴァイアサン』と接続する必要がある。問題は、身体と身体の変様力や活動力が「リヴァイアサン」の巨大な人工的身体(国家)に組み立てられ(モンタージュ)され、配分を受ける配置にあるのだ。ならばどうするか。「リヴァイアサン」の解体によって内戦に戻るのではなく、内戦と対立する和合を組み立てなおすのでもなく、人間の配置をやりなおそうとしたスピノザの延長として、本論文はフリーダ・カーロの絵画、サミュエル・バトラー『エレホン』の「機械の書」、ハンナ・ヘーヒのモンタージュ作品を媒介に、別のモンタージュを構想した。
-
榑沼範久
『常盤台人間文化論叢』 6 ( 1 ) 145 - 158 2020年3月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要) 出版者・発行元:横浜国立大学大学院都市イノベーション学府・研究院 単著
「われわれは海の道—「海上の道」(柳田国男)とはまた別の次元にある海の道—、そして海坂が閉じられた世界に生きている、ということだ。では、いつまでも海の道をとおって通い来る海神の姫の願いを叶えることは、もはやできないのだろうか。海の道が、海坂が閉じられた世界のなかで、海神の姫の願いを聞き届け、その願いを叶えようとするのが、われわれの世界における芸術の使命のひとつではないか。」
「『古事記』では、人間と動物に共通する起源は人間性ではない。それは神代に記録されている人神性なのである。動物が元-人間なのではなく、動物も人間もひとしく元-人神だった。文字通り豊玉姫や山幸彦のような人神だった。その意味で、この国は人間が不在の無人島だった。人間と動物に共通する原初的な条件とは、動物性のことではなく、人間性のことでもなく、人神性なのである。おそらく人間もまた、自らと同じままであり続けた者ではない。」
「大いなる分割によって、人間と動物がともに人神性をいかに失ったのか。この超自然的出来事と、海と陸を行き通うことができたはずの元-人神のありかを、『古事記』は地政的な覇権争いの彼方に物語っている。超自然的な人神たちが渚で夢を混ぜ合わせることができたはずの、社会契約を超えた超自然契約の神話として。人神性からすれば、海坂が閉じられたあとの世界のほうが悪い夢であり、海の道を通い来る願いこそ現実なのだ。われわれは「人新世」以後の地球の新しい法(ノモス)を探るとき、こうした神話に含まれる「貴重な真実」を見る。」 -
「2000年—ボナール、絵画空間の冒険(2000: Bonnard, or A Pictorial Space Odyssey)」
榑沼 範久
『オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展』 2018年9月 [招待有り]
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(その他学術会議資料等) 出版者・発行元:国立新美術館 単著
「ジヴェルニーのモネが逝去し、ボナールとマルトがル・カネに家「ル・ボスケ(茂み)」を購入した翌年の1927年、ラヴクラフトはある短編小説を発表した。春に異様な色の花をつける植物が茂みに出現し、発色する何かがひらひら飛んでいる。風もないのに、壁も窓も揺らめいている。それは私たちの知る自然法則から外れた「宇宙からの色」だった。かたやル・カネを拠点に絵画=生活を弛まず続けるボナールは、戦渦と老化の時間のなか、ひとつの計画ある営みを進めていく。「私はなんとか仕事をしているし、絶対の探求を夢見ています」(マティス宛のボナールの「手紙」1940年)。ボナールが追求する「絶対の探求」とは何だったのか。[…]色が光にならないことを画家は嘆く必要はない。モノリスやスターゲイトから放射される光の運動が、視神経を眩惑、動員する力として侵入するクラーク/キューブリック『2001年宇宙の旅(2001: A Space Odyssey)』(1968)の手前で、絵を描き続けることが大事なのだ。「運動」や「力」に支配された時間を静止させる絵画空間のかたちで。夢想する猫や興奮の合間に眠る犬のまわりで(「手帖」1944)、静かに揺らめく水、肌、色硝子、植物、蝶の羽のように。「芸術作品:時間の静止」(「手帖」1936)とはそういう意味だろう。色彩は幾重にも織り成された反射光を共有しながら、他者との無限の交渉を示す。自然と文化を区別して動員するような、「力」による地上の制圧の歴史とは異なるかたちで。毎日の散歩で「新種の小さな花々の出現」に目をとめながら、「宇宙の構成」に思いを馳せるボナールは(「手紙」1941年)、宇宙的なものにおいて生起する「果てしなく新しい」反応を—「宇宙からの色」を—、この地上の生命圏、生活圏のただなかで化合しようとしているのだ。神学—物理学—戦争の三位一体(トリニティ)によって動員され、製造される「力」とは異なるかたちで。「目を離すな、色が意味あるものに変容する瞬間から」(「手帖」1938年)。目を離すな、ボナールの絵が人類史の転換点から見て、意味あるものに変容する瞬間から。ボナールは原子力開発と「人新世」の時代の画家なのだから。」
-
「20世紀の文化における宇宙的なものの上昇─宇宙機械と人新世の通夜=覚醒のために」
榑沼 範久
常盤台人間文化論叢 4 ( 1 ) 65 - 88 2018年3月 [査読有り]
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要) 出版者・発行元:横浜国立大学都市イノベーション研究院 単著
本論は20世紀の文化が宇宙的なものと集中的に接触しようとしてきたことを、宇宙的なものの上昇とでも呼べる事態が20世紀の文化に生じたことを、いくつかの文化領域における顕著な言説・表現を共振させることによって、新たに描き出すことを目的とする。それは人類史における宇宙的なものとの接触、そして後述する宇宙機械の創造という問題系の布置=星座を、おもに人文学・文化学の視座から構築する筆者の企図の一環をなすものだ。この企図にとって序論的性格をもつのが本論とも言える。20世紀文化史の展開のなかから宇宙的なものとの接触、宇宙的なものの上昇という新しい問題の布置を、まずは大胆に抽出していくことに、本論は主眼を置いている。科学技術の発展にも応じた進歩主義を基調とするモダンの大きな物語=歴史が失墜すると同時に、分割された小さな物語=歴史と国家主義・経済成長主義・宗教原理主義の各種物語が同時に増殖するポストモダン状況の袋小路のなか、モダンを反省する再帰的ポストモダンをも超える、来るべき人類史のベクトルの可能性を描くこと。モダンへの回帰でも、ポストモダンでの停止でもない、いわばポストモダンの超克を、20世紀の文化における宇宙的なものの上昇、そして宇宙機械の創造という人類史の切線によって切り開くこと。こうした人類史の哲学への新たなアプローチが、宇宙的なものと接触しようと試みた20世紀の文化の点と点のいくつかを共振させながら、本論で計られることになるはずだ。
-
「生態学的建築をめざして―建築とギブソンの生態学」
榑沼 範久
『思想』 ( 1045 ) 77 - 107 2011年5月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 出版者・発行元:岩波書店 単著
総説・解説記事等 【 表示 / 非表示 】
-
「人間の可能性を読み解くー「都市のあとに来るもの」へ向けて」
榑沼 範久
『IUI YEARBOOK 2022/2023』 ( Vol. 12 ) 24 - 35 2023年3月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他) 単著
アンリ・ルフェーブルが『都市革命』(1970)で示した社会の「完全な都市化」の仮説は、自然から都市に向かう歴史の図式を依然として前提にしてしまっている。この図式を前提にする限りは、都市を超えるもの、都市のあとに来るものを想像することも思考することもできない。都市とは自然と対極にある完全な人工世界というイメージに、われわれは閉じこめられてしまう。しかし、固定した都市ではなく都市化というプロセスをルフェーブルが重視するならば、自然から都市に向かう歴史の図式よりもむしろ、都市化とは「集めること」を本質にするという『都市革命』の別の論点を重視する必要がある。都市化とは「集めること」である。そしてこの都市化が作動する限り、どの地点も「中枢」になることができる。逆に言えば、都市化が停止した「都市」というものもあるのだ。この論点を拡張することで、われわれは自然から都市に向かう歴史の図式を緩め、解し、完全な人工的都市でも、程よく自然を混ぜ合わせた未来都市でもなく、都市を超えるもの、都市のあとに来るものを想像、思考し、その制作に向かうことができるはずだ。しかしルフェーブル『都市革命』には「集めること」の論理的・具体的な展開が欠けている。そこで後期マルティン・ハイデガーの「四集」する「世界」(四集界)の哲学を、ルフェーブル『都市革命』接続した。ハイデガーの「四集」におけるエレメンツは大地、天空、神的なものたち、死を定められたものたち(人間)である。この四集界の概念の利点は、自然から都市に向かう歴史の図式を前提にすることなく、世界史を思考できることにある。人工と自然を問わず四つのエレメンツの集合の様相を見るのである。やはり人間でなければ辿り着けない奥深い世界がある。四集界の哲学も示すように、その奥深いところには人間だけの力では辿り着けない。都市を超えるもの、都市のあとに来るものもまた、人間にしかきっと作ることができないが、同時に人間だけでは作れないものなのだ。ただしハイデガーの哲学は四つのエレメンツが完全に一つになることを理念とするあまり、世界史の具体相を構想するには不十分である。ハイデガーの概念を組み換えていかなければいけない。
-
「炎を育てよ—栗山斉の系譜」
榑沼 範久
栗山斉『無にみつるもの』 40 - 43 2023年12月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他) 出版者・発行元:(九州⼤学⼤学院芸術⼯学研究院 単著
蛍光灯、ネオン灯、ガラス管、鉛鏡、ステンレス、アルミニウム、シリコン、電線、LED、真空、大気圧などを使用する 《0=1-another》《0=1-filament blue》《真空の種》《symbiosis》《真空トンネル》など栗山斉氏(九州大学大学院芸術工学研究科准教授)の作品を、芸術と科学が分割されることのないSF(スペキュラティヴ・フィクション)の世界制作と見立てた。そして、完全な無としての真空が存在するかどうかを論争するのではなく、改良を重ねた空気ポンプで可能な限り空気を抜いたものを「真空」と見なし、そこに実在するものを実験室に入る誰もが見ることができるようにしたロバート・ボイルの系譜に、栗山作品を位置付けた。この系譜には、マイケル・ファラデーがロンドンの王立研究所で行った有名な連続講演「ロウソクの化学史」(ロウソクの科学)を目の当たりにした者たち、なかでもその講演を熱心に記録し、序文を寄せたウィリアム・クルックスもいる。ファラデーの講演に「〈学(サイエンス)の光明(ランプ)〉」を灯されたクルックスは、ボイルの意匠を受け継ぐ真空管(クルックス管)を制作して電気を放ち、陰極線(真空中を陰極から高速度で陽極に向かう電子の流れ)を可視化することに成功した。さらには、クルックス管から放射される不思議な電磁波をヴィルヘルム・レントゲンはX線と名づけ、見えるものと見えないものの分割を、誰の目にも明らかなすがたで動かしてみせたのだ。ファラデー「ロウソクの化学史」の序文を結ぶクルックスの言葉を、この系譜の未来に灯したい。「〈学(サイエンス)の光明(ランプ)〉を燃やさなければならない。」「炎を育てよ(Alere Flammam)。」
-
「地盤の表象化とモデル化について」
菊本統+榑沼範久
『IUI YEARBOOK 2021/2022』 2022年3月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:その他 単著
安政の大地震以後に流行した鯰絵を、近代科学以前の迷信と見なすのではなく、制御の難しい地質の具体性を象徴する的確な見立てとして把握しなおすことから、地盤を把握する方法と諸相をめぐる問題提起を行った。鯰絵と対比すべきは、放射性廃棄物の最終処理場の図である。地下深くまで建造される処理場の構造は概観できるものの、その構造体の環境である肝心の地質がホワイトアウトあるいはブラックアウトしてしまっている。これは近代科学を牽引した天文学者の「環世界」(ユクスキュル)の挿絵にも共通点がある。天文学者が生きているはずの地球環境がブラックアウトしているのである。ならば、地質学者の「環世界」はいかなるものか。この問いはこれからの人類にとってますます重要な問題になると考え、現代の地盤力学者にそれを問いかけることになった。また、近代科学の進展する同時代に、芸術家、思想家、地質学者たちは、どのように大地を、地質を、地盤を把握し、表象してきたのか。レオナルド、キルヒャー、ゴッホ、ムンク、セザンヌ、ヴェルヌ、ダーウィンを例に事例をたどった。また、現代日本の大地表象として、小松左京『日本沈没』に登場する異能の地震学者の仮説を論じ、対談相手である現代の地盤力学者がどう大地をモデル化、数値化するか、その視座や手法と対比させながら語り合った。
-
榑沼範久
栗山斉「内なる無限の宇宙」展パンフレット 2019年12月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他) 出版者・発行元:ART FRONT GALLERY 単著
栗山斉「内なる無限の宇宙」を観るわれわれは、不完全な「暗い星」を抱握しようとする、それぞれ不完全な「暗い星」になるのかもしれない。不完全とは、否定的な意味で言うのではない。作者も作品も観客も完全なるものではなく、いずれもが活動する実在として、ある程度は制御された禍々しさとして、ギャラリー(不完全に明るい部屋、不完全に暗い部屋)で衝突し、何ものかを限定的に合生させるのだから。「内なる無限の宇宙」が設置された不完全に無音なギャラリーのなかで、見えない内なる音がわたしに聴こえてくるならば、それはキング・クリムゾン「アスピックゼリーに入るヒバリの舌(Part I)」(Lark’s Tongues in Aspic, 1973)—いまにも壊れそうな制御された空間のなかで、切断や陥没や屈曲や消散の可能性を予期させながら微粒子が揺動し、ガラスや金属の結晶がこすれ合う音—に近似するのかもしれない。あるいは、「破砕(Fracture)」(Starless and Bible Black, 1974)—静謐なエネルギーだまりの沈黙を突然、理由もなく烈しく破って旋回していく音—や、それが消滅したあとにおそらく持続する、色とりどりの「無音」の痕跡や軌跡に。あるいは、「暗い星が衝突する、その光を灰に注いで/理由は裂け、諸力は枢軸から剥離する」「物質の無形の反射のなかで鏡は粉々になる/旋回する氷状の弁花へと溶解するガラスの束」(グレイトフル・デッド「Dark Star」、『LIVE/DEAD』、1969)のごとく。
その他リンク: https://www.artfrontgallery.com/exhibition/archive/2019_10/3956.html
-
榑沼範久
10+1 website 2017年8月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア) 単著
作品・芸術・データベース等 【 表示 / 非表示 】
-
地球と建築2
石上純也、榑沼範久
2012年1月
作品分類:その他
-
地球と建築1
平田晃久、藤本壮介、榑沼範久
2012年1月
作品分類:その他
-
三上晴子 欲望のコード|アーティスト・トーク
三上晴子、池上高志、榑沼範久、畠中実
2011年12月
作品分類:その他
-
これから生まれる建築と生態のために2
平田晃久、榑沼範久
2010年12月
作品分類:その他 発表場所:北仲スクール/ヨコハマ創造都市センター
-
これから生まれる建築と生態のために
藤本壮介、榑沼範久
2010年10月
作品分類:その他 発表場所:北仲スクール/ヨコハマ創造都市センター
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
下村寅太郎の「潜在的著作」を集成する
2020年4月 - 2026年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
代表者:榑沼範久
資金種別:競争的資金
京都学派の著名な哲学者である下村寅太郎(1902-1995)は、1973年の定年退職後も著述活動とは別に、自身の研究談話会「プリムツァール会」で広大な思索を録音テープに残していた。「真の著作遍歴は著作以外にあるとすらいえる」、「テープの存するかぎり潜在的著作と称してもよいであろう」とは下村自身の言である。だが、『下村寅太郎著作集』(1988-1999)の完結から20年以上が過ぎた現在でも、この「潜在的著作」は公刊されていない。録音された音声を文字化し、選択・校閲・編集を経て刊行を目指す本研究は、下村の未知の側面の発見にとどまらず、日本近代思想史の研究にとっても重要な学術資料の集成になるだろう。
-
戦争と芸術論
2004年4月 - 2005年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
代表者:木下長宏
資金種別:競争的資金
「戦争」は人類の歴史を貫通する重大事であり、つねに最も根源的な社会変容の契機となり、その結果でもあり、人間性に関わる出来事として、人間の生活・思索活動に多大な影響を与えてきた。「芸術活動」ももちろんその例外ではない。従来、芸術史・芸術論の分野では、限られた時点での戦争と芸術表現に関する個別的な研究(例えば、「第二次世界大戦における戦争画の研究」、「翼産体制下の文学」など)は深められてきたが、われわれはそうした個別研究の成果・蓄積を踏まえて、「戦争」という人類にとって不可避とも言うべき行動を、広く地球上に見わたし、近代から現代という時代において、その行動が芸術と呼ばれる領域のなかで、どのように受け取られ、また社会へ返されていったかを「思想」のありかたとして追及して行こうとしている。戦争と「芸術論」と敢えて題したのは、そのような意味での広義の思想的活動に焦点を絞ろうとしたからである。いいかえれば、結果としての作品(海外、映像、詩、小説、音楽など)にではなく、そうした作品が作られ、それが享受され後世に受け継がれていく過程総体のなかで、「戦争」との関わりを解き明かそうとするものである。
研究発表 【 表示 / 非表示 】
-
下村寅太郎の「潜在的著作」―プリムツァール会の録音テープについて
榑沼 範久 [招待有り]
日本哲学史フォーラム 2024年10月 京都大学文学研究科日本哲学史専修
開催年月日: 2024年10月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:京都大学
-
小宮山恵三郎氏インタビュー「下村寅太郎の記憶―よみがえる哲学者の声とその近辺」
小宮山恵三郎、上原麻有子(インタビュアー)、榑沼範久(インタビュアー) [招待有り]
日本哲学史フォーラム 2024年10月 京都大学文学研究科日本哲学史専修
開催年月日: 2024年10月
記述言語:日本語 会議種別:その他
開催地:京都大学
-
青木繁《海の幸》(1904[明治37]年)を考える
榑沼 範久
生物文化多様性ラボセミナー 2024年11月 横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ
開催年月日: 2024年11月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:横浜国立大学
-
「われわれはみな地衣類」なのだろうか?
榑沼 範久
生物文化多様性ラボセミナー 2024年5月 横浜国立大学総合学術高等研究院生物圏研究ユニット生物文化多様性ラボ
開催年月日: 2024年5月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:横浜国立大学
-
榑沼 範久 [招待有り]
地衣類研究会オンライン地衣類講座 2024年4月 地衣類研究会
開催年月日: 2024年4月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(招待・特別)
開催地:オンライン(Zoom)
都市の現在と未来を考える授業で、『廃墟のロビンソン』(パトリック・キーラー監督、2010)という英国の映画を観ていたときのことです。道路標識に付着する地衣類がくりかえし映し出されていました。翌月には地衣類研究会入会申込書を送りました。2022年の8月のことです。過去に自分はダーウィンに関する文章を書いたことがあるにしても、なぜこれほど地衣類に惹かれたのか。(人文学者の私が)地衣類に関心を抱く理由を話してみたいと思います。ただし、地衣類に共生の理想を投影するのではなく。地衣類に「共生」「他利」「抵抗」「美醜」を見るよりむしろ表面性、断片性、不定形、(生態系全体にとっての)”無用性”を積極的に認識する必要を感じています。地衣類は例えば菌根や菌糸のネットワークと異なり、森の生態系に寄与するわけではなく、付着した樹木と共生関係を結ぶわけでも、寄生関係を結ぶわけでもなく、樹皮であろうとコンクリートであろうと金属製の人工物であろうと無関係に、ただ付着しています。自然/生態系/ガイア全体の一部でなく、そこからただ外れた生命のありかたとして見ること、惑星生物学の対象としての生物であると提唱したいのです。『生態進化発生学: エコ-エボ-デボの夜明け』の著者の一人、スコット・F・ギルバートは共著論文(Scott F. Gilbert, Jan Sapp and Alfred I. Tauber, “A Symbiotic View of Life: We Have Never Been Individuals,” 2012)の最後を“We are all lichens(われわれはみな地衣類である)”と結んでいます。しかし、個体内外における生物的共生の全体のなかに地衣類を代表者として還元するのは、前述した地衣類の特徴を消去することになるのではないでしょうか。自然/生態系/ガイア全体の一部でなく、そこからただ外れた生命のありかた。これが例外ではない生命の概念にわたしたちが到達したとしたら、そのときこそ“We are all lichens(われわれはみな地衣類である)”と言うことができるはずです。
担当授業科目(学内) 【 表示 / 非表示 】
-
2025年度 文化創成スタジオAⅡ
都市科学部
-
2025年度 文化創成スタジオAⅠ
都市科学部
-
2025年度 空間芸術論講義
都市科学部
-
2025年度 空間文化論講義
都市科学部
-
2025年度 空間芸術論演習Ⅱ(英語)
都市科学部
担当経験のある授業科目(学外) 【 表示 / 非表示 】
-
メディア概論
2008年4月 - 現在 機関名:東京藝術大学
-
芸術学C
2018年4月 - 現在 機関名:慶應義塾大学
-
今、都市を考える
2022年10月 機関名:放送大学
この地球という惑星に誕生したサピエンスの歴史のなかで、都市とは果たして何だったのでしょう か。今、都市はどうなっているのでしょうか。そして都市の未来はどうなっていくのでしょうか。どうな る必要があるのでしょうか。都市は自由の場所でしょうか。孤独と病の源泉でしょうか。欲望と富の 集積地でしょうか。文化と文明の発信地でしょうか。攻撃や防衛の対象でしょうか。環境の最大の 破壊者でしょうか。都市はサピエンスだけのものでしょうか。こうした問いを立てながら、今、都市に ついて考えるべきことを探っていきたいと思います。
第1回 自分史のなかの都市を語る
第2回 今、都市をめぐり話し合う
第3回 「祝祭都市の政治」から展開する
第4回 「揺らぐ都市へ/から」「都市という謎にせまる」から展開する
第5回 「ユートピアかディストピアか」から展開する
第6回 「都市のスケールとリズムについて」から展開する
第7回 「イスラーム都市から考える」から展開する
第8回 「都市と世界を揺らす」から展開する
(教科書:『都市は揺れているー五つの対話』(吉原直樹・榑沼範久/都市空間研究会編、東信堂、2020年) -
<世界史>を改めて考える
2021年12月 機関名:放送大学
-
テクノロジー文化論
2013年4月 - 2023年9月 機関名:武蔵大学
社会活動(公開講座等) 【 表示 / 非表示 】
-
山森裕毅『フェリックス・ガタリの哲学』合評会
役割:出演, 運営参加・支援
DGラボ 山森裕毅『フェリックス・ガタリの哲学』合評会 横浜国立大学都市科学部講義棟103 2025年3月
対象: 大学生, 教育関係者, 研究者, 社会人・一般
種別:会議、学会等の企画・開催
-
講義「海と陸をつなぐ道〜『古事記』から出発して〜」
役割:講師
東京都立新宿高等学校 東京都立新宿高等学校出張講義 2024年10月
-
日建設計PYNT×横浜国立大学「まちづくり:未来の"境界"をさぐる」(全4回)
役割:コメンテーター, 司会, 企画
横浜国立大学総合学術高等研究院豊穣な社会研究センター、日建設計PYNT 「まちづくり:未来の"境界"をさぐる」 2024年9月 - 2025年3月
-
「「ここは天国にも地獄にもなりうる」:厄災のなかのパラダイスに向けて」
役割:パネリスト, 司会
豊穣な社会研究センター/横浜国立大学 防災KOKUDAI 2023年9月
種別:フェスティバル
災害が起きたときの私たちの命運は、死生観を含む私たちの生き方によって大きく変わるだろう。私たちが豊穣な社会に向けて目指しうる人間の在り方、そして、つながり方を議論した。なお、議論をするに先立ち、このフェスティバルに集まった人たちと言葉やイメージを最初に共有するところから議論を始めるために、テーマに関連する複数の言葉、複数の声を集めて朗読する「朗読劇」を上演した。取り上げた言葉の出典は寺田寅彦『柿の種』「災難雑考」、渡辺憲司『海を感じなさい 次の世代を生きる君たちへ』、石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣病』、レベッカ・ソルニット『災害ユートピア なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか』、吉村昭『関東大震災』『三陸海岸大津波』、藤本和子『塩を食う女たち 聞書・北米の黒人女性』、ナタリー・サルトゥー=ラジュ『借りの哲学』、森健『「つなみ」の子どもたち 作文に書かれなかった物語』、『表現者クライテリオン』特集「思想としての防災」、ジェームズ・C・スコット『実践 日々のアナキズム 世界に抗う土着の秩序の作り方』、ナオミ・クライン『楽園をめぐる闘い 災害資本主義者に立ち向かうプエルトリコ』など。司会進行:榑沼 範久、朗読者:有馬 優、榑沼 範久、細田 暁、パネラー:佐藤 千恵(客員教授)、松永 昭吾(客員教授)、細田 暁(センター長)。
-
「豊穣な未来社会へ、災害を媒介に」
役割:出演, 司会
豊穣な社会研究センター/横浜国立大学 防災KOKUDAI 2023年9月
種別:フェスティバル
防災の重要性に異論はない。ただ、私たちは防災という言葉を使った瞬間に災害を敵とみなし、敵からの防衛に意識を集中させてしまう...。まるで敵がいなくなれば問題がなくなるかのように。しかし災害とはむしろ、私たち自身を映し出す鏡ではないか。この鏡を媒介に、来るべき私たちの未来社会を考える。なお、議論をするに先立ち、このフェスティバルに集まった人たちと言葉やイメージを最初に共有するところから議論を始めるために、テーマに関連する複数の言葉、複数の声を集めて朗読する「朗読劇」を上演した。取り上げた言葉の出典はカレル・チャペック『山椒魚戦争』、ヴァルター・ベンヤミン「歴史の概念について」、ジェームズ・C・スコット『実践 日々のアナキズム』、レベッカ・ソルニット『災害ユートピア』、小松左京「地球社会学の構想」「廃墟の空間文明」、寺田寅彦『柿の種』、鶴見俊輔『方法としてのアナキズム』、吉本隆明「南島論序説」、ナタリー・サルトゥー=ラジュ『借りの哲学』、武田邦彦『これからの日本に必要な「絡合力」』、ダナ・ハラウェイ『犬と人が出会うとき 異種恊働のポリティクス』、渡辺憲司『海を感じなさい』、ヘンリー・デイヴィッド・ソロー「現代の商業精神」、マルセル・プルースト『失われた時を求めて』、ハンナ・ア―レント『活動的生』、スタニスワフ・レム『ソラリス』など。司会進行:榑沼 範久、朗読者:有馬 優、榑沼 範久、細田 暁、パネラー:細田 暁(センター長)、松永 昭吾(客員教授)、河野 克典(客員教授)、佐藤千惠(客員教授)
メディア報道 【 表示 / 非表示 】
-
OTTAVA「今夜もウェルネス!」#72 出演
OTTAVA 今夜もウェルネス! 2021年5月
最晩年(50代半ば)のルートヴィヒ・ファン・ベートーヴェン(1770-1827)が『交響曲第9番』(1824年)のあとに集中して取り組んだ弦楽四重奏曲、そのなかでも亡くなる前の年(1826年)に完成させた2曲を取り上げる。フランツ・シューベルト(1797-1828)、物理学者ロバート・オッペンハイマー(1904-1967)、そしてミラン・クンデラの小説『存在の耐えられない軽さ』(1984)も話に交差させながら聴く曲は、ベートーヴェン「弦楽四重奏曲 第14番」(作品131)、「弦楽四重奏曲 第16番」(作品135)から。
-
OTTAVA「今夜もウェルネス!」#64 出演
OTTAVA 今夜もウェルネス! 2020年3月
不確実に揺れ動く社会と世界のなかで、さまざまな人生の嵐や病と向き合いながら、まだ聴こえない音楽を追究していくロベルト・シューマン(1810-1856)について語る。取り上げる曲は、オーボエとピアノのための「3つのロマンス」Op.94(1849)、ホルンのための「アダージョとアレグロ」Op.70(1849)、「チェロ協奏曲」Op.129(1850)など。
-
OTTAVA「今夜もウェルネス!」#61 出演
OTTAVA 今夜もウェルネス! 2020年2月
グスタフ・マーラー作曲、交響曲第9番(1909)、第4楽章アダージョ(緩徐楽章)の聴きどころと、なぜマーラーの楽曲がいまだ私たちにリアルに響くのか、その歴史的・社会的な意味を中心に語る。
-
OTTAVA「今夜もウェルネス!」#60 出演
OTTAVA 今夜もウェルネス! 2020年2月
グスタフ・マーラー作曲『大地の歌』(1908)の聴きどころと、科学と芸術を横断するその楽曲の文化史的位相を中心に語る。
-
東京藝術大学 先端○展 公開講評会
東京藝術大学先端芸術表現科 東京藝術大学上野校地 絵画棟1階 アートスペース 2016年12月
東京藝術大学先端芸術表現科1年生の展覧会(先端◯展)の最終日に開催された公開の作品講評会・講評者。
学内活動 【 表示 / 非表示 】
-
2021年04月-2023年3月都市科学部 都市社会共生学科 学科長 (その他の主要活動)
-
2024年04月-2025年3月都市イノベーション研究院建築都市文化専攻都市文化系(芸術文化系)Y-GSCスタジオ代表 (その他の主要活動)

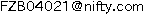


 ORCID
ORCID