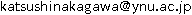|
Affiliation |
Faculty of Urban Innovation, Division of Urban Innovation |
|
Job Title |
Associate Professor |
|
Date of Birth |
1975 |
|
Research Fields, Keywords |
Sound Art, Sound Studies, Sound Media Studies, Sound Studies, Contemporary Music |
|
Mail Address |
|
|
Web Site |
|
|
Related SDGs |
NAKAGAWA Katsushi
|
|
|
The Best Research Achievement in Research Career 【 display / non-display 】
-
【Book】 サウンド・アートとは何か : 音と耳に関わる現代アートの四つの系譜(ナカニシヤ出版) 2023
【Book】 音響メディア史 2015.05
【Book】 ジョナサン・スターン 2015(2003) 『聞こえくる過去:音響再生産の文化的起源』 2015.10
The Best Research Achievement in the last 5 years 【 display / non-display 】
-
【Book】 サウンド・アートとは何か : 音と耳に関わる現代アートの四つの系譜(ナカニシヤ出版) 2023
【Published Thesis】 クリスチャン・マークレー再論:世界との交歓(東京都現代美術館(編) 2022 『クリスチャン・マークレー:トランスレーティング[翻訳する]』(東京都現代美術館、2021年11月20日-2022年2月23日) 展覧会図録 東京:左右社) 2022.04
【Published Thesis】 日本における〈音のある芸術の歴史〉を目指して――1950-90年代の雑誌『美術手帖』を中心に――(細川周平(編)『音と耳から考える:歴史・身体・テクノロジー』(アルテスパブリッシング)) 2021.10
【Published Thesis】 History of Sound in the Arts in Japan Between the 1960s and 1990s 2021.03
【Published Thesis】 The Preparatory Research on Sound Art in Taiwan: The Case of WANG Fujui 2021.03
Education 【 display / non-display 】
-
-2006.3
Kyoto University Dept. of Aesthetics and Art History Doctor Course Accomplished credits for doctoral program
Campus Career 【 display / non-display 】
-
2011.4
Duty Yokohama National UniversityFaculty of Urban Innovation Division of Urban Innovation Associate Professor
-
2017.4
Concurrently Yokohama National UniversityCollege of Urban Sciences Department of Urban and Social Collaboration Associate Professor
-
2011.4
Concurrently Yokohama National UniversityGraduate School of Urban Innovation Department of Architecture and Urban Culture Associate Professor
-
2011.4
Concurrently Yokohama National UniversityGraduate School of Urban Innovation Department of Urban Innovation Associate Professor
External Career 【 display / non-display 】
-
2005.7-2006.6
University of California, Davis Technocultural Studies of Art Department Visiting Researcher
Academic Society Affiliations 【 display / non-display 】
-
2012.10
Japanese Association for Studying Popular Music
-
2000.4
The Japanese Society for Aesthetics
-
2000.4
International Congress of Aesthetics
Research Career 【 display / non-display 】
-
Elucidating the Relationships between Music, Visual Arts, and Sound Art during the Emergences of Sound Art in Japan, Taiwan, and the Western
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2024.4 - 2027.3
-
Establishment of a foundation for sound art research based on East Asian examples
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2020.4 - 2024.3
-
台湾における「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」の系譜の研究:王福瑞の事例を中心に
Grant-in-Aid for Promotion of Private Scientific Research
Project Year: 2019.4 - 2020.3
-
The development of Sound Art in Japan in the 1980s
Project Year: 2015.4 - 2018.3
-
クリスチャン・マークレイ研究—サウンド・アートの系譜学
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2012.4 - 2015.3
Books 【 display / non-display 】
-
( Role: Sole author)
( ISBN:9784779517730 )
Language:Japanese Book type:Scholarly book
-
History of Sound Media
TANIGUCHI Fumikazu, NAKAGAWA Katsushi and FUKUDA Yudai( Role: Joint author)
Nakanishiya Syuppan ( ISBN:9784779509513 )
Total pages:334 Language:Japanese Book type:Scholarly book
-
サウンド&アート展 : 見る音楽、聴く形 = sound & art : performance/workshop
毛利 嘉孝, 中川 克志, 廣川 暁生, 明石 薫, クリエイティブ・アート実行委員会( Role: Sole author)
クリエイティブ・アート実行委員会2021
Language:Japanese Book type:General book, introductory book for general audience
-
Computational Aesthetics(SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology)
Yasuhiro Suzuki, Katsushi Nakagawa, Takashi Sugiyama, Fuminori Akiba, Eric Maestri, Insil Choi, and Shinya Tsuchiya.( Role: Joint author , A Brief Consideration About the Relationship Between Sound Art and Tactile Sense.)
Springer ( ISBN:9784431568421 ) [Reviewed]
Total pages:96 Responsible for pages:53-65 Language:English Book type:Scholarly book
NAKAGAWA Katsushi. 2018. "A Brief Consideration About the Relationship Between Sound Art and Tactile Sense." In: Computational Aesthetics. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Tokyo: 53-65.
-
アメリカ文化事典:アメリカ学会(編)
アメリカ学会(編)( Role: Joint author , 「実験音楽」(「17.音楽・舞台」収録))
丸善出版(東京) ( ISBN:9784621302149 )
Total pages:960 Responsible for pages:692-693 Language:Japanese Book type:Dictionary, encyclopedia
Thesis for a degree 【 display / non-display 】
-
Music as Listening - American Experimental Music beyond John Cage
Katsushi Nakagawa
2008.3
Doctoral Thesis Single Work
-
"A study on the minimalism in the early works of Steve Reich" (MA thesis, 2000, Univ. of Kyoto, in Japanese)
Katsushi Nakagawa
2000.3
Master Thesis Single Work
Papers 【 display / non-display 】
-
Music and Visual Art: An Essay: Three Turning Points
NAKAGAWA Katsushi
Kansai Journal of Aesthetics and Musicology 9 2 - 20 2025.3 [Invited]
Authorship:Lead author Language:Japanese Publishing type:Research paper (bulletin of university, research institution) Single Work
-
An Introduction to Music Epistemology: Exploring the Boundaries of Sound and Music since John Cage
NAKAGAWA Katsushi
Tokiwadai journal of human sciences 11 ( 1 ) 107 - 123 2025.3
Language:Japanese Publishing type:Research paper (bulletin of university, research institution) Publisher:Yokohama National University Faculty of Urban Innovation Single Work
(Due to lack of space, only the first half of this paper will be published here. The latter half will be published in the next volume. However, the abstract below is an abstract of the entire paper.)
This article delves into the history and mechanics of establishing the boundaries between sound and music following the 'revolution' initiated by John Cage in the 1950s, when John Cage introduced the notion of omnipotence in dealing with all kinds of sounds within musical activities. To scrutinize these boundaries, this article assesses John Cage's contributions and emphasizes that the axis Cage set as 'all sounds can be music' has been commonly interpreted as 'all sound is music.' As a case in point, this article provides an overview of three movements in the 1970s that incorporated environmental sounds into the realm of music. The influence of Cage not only garnered supporters but also opponents. The opponents can be divided into two factions. One sought to safeguard the traditional domain of music and exclude Cagean experimental music activities from it (Chris Cutler), while the other aimed to establish art of sound (or sound art) as a distinct field and exclude Cagean activities from sound art (Dan Lander). The underlying concept in operation here can be termed the 'Musicalization of sound.'
This article scrutinizes the cognitive framework governing the relationship between the acoustic continuum and Cagean experimental music. It aspires to position this discourse within a historical context and convey the message that it is time to finish discussions concerning the boundary between sound and music. Instead, we should foster fresh practices and dialogues that transcend these boundaries. -
An Introduction to Music Epistemology: Exploring the Boundaries of Sound and Music since John Cage
NAKAGAWA Katsushi
Tokiwadai journal of human sciences 10 ( 1 ) 145 - 160 2024.3
Language:Japanese Publishing type:Research paper (bulletin of university, research institution) Publisher:Yokohama National University Faculty of Urban Innovation Single Work
(Due to lack of space, only the first half of this paper will be published here. The latter half will be published in the next volume. However, the abstract below is an abstract of the entire paper.)
This article delves into the history and mechanics of establishing the boundaries between sound and music following the 'revolution' initiated by John Cage in the 1950s, when John Cage introduced the notion of omnipotence in dealing with all kinds of sounds within musical activities. To scrutinize these boundaries, this article assesses John Cage's contributions and emphasizes that the axis Cage set as 'all sounds can be music' has been commonly interpreted as 'all sound is music.' As a case in point, this article provides an overview of three movements in the 1970s that incorporated environmental sounds into the realm of music. The influence of Cage not only garnered supporters but also opponents. The opponents can be divided into two factions. One sought to safeguard the traditional domain of music and exclude Cagean experimental music activities from it (Chris Cutler), while the other aimed to establish art of sound (or sound art) as a distinct field and exclude Cagean activities from sound art (Dan Lander). The underlying concept in operation here can be termed the 'Musicalization of sound.'
This article scrutinizes the cognitive framework governing the relationship between the acoustic continuum and Cagean experimental music. It aspires to position this discourse within a historical context and convey the message that it is time to finish discussions concerning the boundary between sound and music. Instead, we should foster fresh practices and dialogues that transcend these boundaries. -
Study on the Genealogy on Sound Art in Japan: Focusing on the Case of Kyoto International Contemporary Music Forum (1989-1996)
11 44 - 53 2024
Language:The in addition, foreign language Publishing type:Research paper (scientific journal) Single Work
-
日本におけるサウンド・アートの系譜学:神戸ジーベックホール(1989-1999)をめぐって:その1――『Sound Arts』誌(1992-1998)の場合――
中川 克志
京都国立近代美術館研究論集 CROSS SECTIONS 11 44 - 53 2024
Language:The in addition, foreign language Publishing type:Research paper (scientific journal) Single Work
Review Papers 【 display / non-display 】
-
ジョナサン・スターン 2015(2003) 『聞こえくる過去:音響再生産の文化的起源』
中川克志・金子智太郎・谷口文和(訳)
インスクリプト 60 - 75 2015
Language:Japanese Publishing type:Article, review, commentary, editorial, etc. (other) Joint Work
-
[書評] 庄野進著『聴取の詩学 枠と出来事 庄野進音楽美学論集』(春秋社、2024年)
中川克志
週刊読書人 ( 20250314号 ) 2025.3
Language:Japanese Publishing type:Book review, literature introduction, etc. Single Work
-
[翻訳]ジョナサン・スターン+メハク・ソーニー「アクースマティックな問いとデータ化の意志——Otter.ai・低リソースな言語・機械聴取のポリティクス」
ジョナサン・スターン, メハク・ソーニー, 中川克志
学術誌『メディウム』 5 163 - 196 2024.12
Language:Japanese Publishing type:Other Single Work
-
[書評] 豊田泰久(語り手)、林田直樹(聞き手)、潮博恵(解説)『コンサートホール×オーケストラ 理想の響きをもとめて』(アルテスパブリッシング、2024年)
中川克志
週刊読書人 ( 20240607号 ) 2024.6
Language:Japanese Publishing type:Book review, literature introduction, etc. Single Work
-
座談会 「音」と文学――文学研究とサウンド・スタディーズとの対話――
福田貴成、中川克志、疋田雅章、広瀬正
昭和文学研究 88 2 - 23 2024.3
Language:Japanese Publishing type:Rapid communication, short report, research note, etc. (scientific journal) Single Work
Works 【 display / non-display 】
-
三沢洋紀と岡林ロックンロール・センター『サイレントのとんがり』
三沢洋紀、岡林コゾー、中川克志、宮地健作
2013.9
Work type:Artistic work Location:Headz
羅針盤、渚にてと並び関西三大うたものバンドと称されたラブクライの中心人物で、ラブクライ活動休止後はPONY、LETTER、三沢洋紀とゆふいんの森、真 夜中ミュージックといったバンドで活動し、昨年は柴田聡子の1stアルバム『しばたさとこ島』、今年は都市レコード『road to you』のプロデューサーとして、その音楽的才能を遺憾無く発揮した三沢洋紀。
彼が、THE BITE / U.G MANの岡林コゾウ大輔、OKミュージックボールの中川克志、ラブクライのメンバーでもあった宮地健作と結成したバンド、三沢洋紀と岡林ロックンロール・ センターが、2012年7月発売のCD-Rの8曲入りアルバム『三沢洋紀と岡林ロックンロール・センター』に続き、ファースト・フル・アルバムを完成させた。
三沢洋紀にとって、プレスCDとしては2012年2月発売の『真夜中ミュージック』(限定300枚)、全国流通盤としては2009年の『三沢洋紀とゆふいんの森』以来となる本作は、プロデューサーにKIRIHITO、GROUP、younGSoundsのメンバーとして、刺激的なサウンドを追求し続けている竹久圏を起用。予てからお互いの活動に注目していたという二人がここ数年で急接近し、三沢にとっては念願の竹久とのコラボレートが実現する こととなった。
ラブクライ時代から定評のある三沢のソングライティング能力やポップ・センスは更に磨かれ、ギター・プレイヤーとしても参加した竹久のハードコアやクラブシーンにも精通した不良性の高い歪な音像やリズム・センス、ジャンルを超越したオルタナティヴなエッセンスによって、単なるうたも の作品では味わうことの出来ない多彩な魅力が詰まった傑作アルバムとなった。
録音、ミックス、マスタリングは近年のテニスコーツやマジキック作品には欠かせない存在となっているサウンド・アーティスト、大城真が担当。
三沢の甘いヴォーカルといぶし銀なバンド・アンサンブルによる、アーシーかつアーバンというアンビヴァレンツなサウンドが奇跡的に融合した、今の日本では他に例を見ない、洒脱な大人のロックンロール・アルバムに仕上がっている。
人生の酸いも甘いも知り尽くした男達が奏でる、この豊潤なバンド・サウンドにどっぷりと酔いしれて欲しい。
Grant-in-Aid for Scientific Research 【 display / non-display 】
-
Elucidating the Relationships between Music, Visual Arts, and Sound Art during the Emergences of Sound Art in Japan, Taiwan, and the Western
Grant number:24K03444 2024.4 - 2027.3
Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Authorship:Principal investigator Grant type:Competitive
-
Establishment of a foundation for sound art research based on East Asian examples
2020.4 - 2024.3
Grant-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Investigator(s):NAKAGAWA Katsushi
Grant type:Competitive
-
サウンドアート学確立による20世紀アート史の書き換え
2018.6 - 2021.3
科学研究費補助金 Grant-in-Aid for challenging Exploratory Research
Investigator(s):中川眞(大阪市立大学 都市研究プラザ 特任教授)
Grant type:Competitive
課題番号:18K18488
研究分野:中区分1:思想、芸術およびその関連分野
研究機関:大阪市立大学 -
日本におけるサウンド・アートの成立過程の調査
2015.4 - 2018.3
科学研究費補助金 Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Investigator(s):中川 克志
Grant type:Competitive
本研究「日本におけるサウンド・アートの成立過程の調査」の目的は、日本においてサウンド・ アートが登場してきた経緯の調査である。「サウンド・アート」という言葉が盛んに使われるよう になった 19 80 年代を中心に、(1)インタビュー調査 と(2)文献調査を行う。日本におけるサウ ンド・アートの登場に関す る先行研究はほとんど存在しないため、本研究では基礎的な資料の収 集整備を重視する。また、その成果を、 日本より 10 年ほど遅れてサウンド・アートを制作するよ うになった(3)台湾、香港、韓国などの状況と比較す ることで、日本におけるサウンド・アート の文化的位置づけの独自性の考察を試みる。これらの研究を通じて 、「日本におけるサウンド・ アート」に関する研究と、日本における「サウンド・アートに関する研究」に貢 献したい。
-
パーソナル・ファブリケーション以降の芸術表現に向けた視聴覚メディアの系譜学
2015.4 - 2017.3
科学研究費補助金 Grant-in-Aid for challenging Exploratory Research
Investigator(s):城一裕(情報科学芸術大学院大学・メディア表現研究科・講師)
Grant type:Competitive
課題番号:15K12842
研究分野:人文学, 芸術学, 芸術一般
研究機関:情報科学芸術大学院大学
Other external funds procured 【 display / non-display 】
-
台湾における「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」の系譜の研究:王福瑞の事例を中心に
2019.4
Private Foundations 稲盛研究助成
Investigator(s):中川克志
本研究は、1990年代初頭に始まった台湾における「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」の歴史について、その始まりから現在に至る系譜を明らかにしようとするものである。本研究では、台湾におけるサウンド・アートのパイオニアの一人である王福瑞の活動を中心に調査する。彼の活動を軸として予備調査に基づいてリストアップした「2.内容」の人々にインタビュー調査を行うことで、90年代から現在に至る台湾におけるサウンド・アートの概要を明らかにできるだろう。この領域の研究はまだほとんど整備されておらず、本研究には一次資料を準備するという意義がある。
台湾におけるサウンド・アートの特徴は、戒厳令が解除された90年代以降に展開したことである。また、日本や欧米では「サウンド・アート」と呼ばれる音を用いる視覚美術だけではなく、日本や欧米で80年代頃に登場した「ノイズ・ミュージック」と呼ばれる音楽もまた、「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」という名称で言及されることも特徴である。これらの特徴は、日本、香港、欧米、中華人民共和国等の相互影響関係の中から生じたトランスナショナルな性格を示すものとして、重要である。本研究には、アジア諸国の文化の相互影響関係の事例研究である、という意義もある。
それゆえ、本研究は、まず第一に、台湾における「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」の系譜において諸活動がどのような布置を形成しているかを探り、第二に、それらがアジア諸国のなかでどのようなトランスナショナルな力学のもとで形成されてきたのか、ということを明らかにしたい。本研究は、究極的には、アジアにおける西洋化と近代化にかかわる文化のメカニズムの解明に貢献せんとするものである。
Presentations 【 display / non-display 】
-
NAKAGAWA Katsushi
국제학술대회가 성황리에 마무리되었습니다.함께해주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 아래에 학술대회 현장의 사진을 공유합니다. 2025.3
Event date: 2025.3
Language:English Presentation type:Oral presentation (general)
Country:Korea, Republic of
-
The comparative study between environmental music in 1980s Japan and Kankyō Ongaku in 2010s Japan
NAKAGAWA Katsushi
IASPM-SEA & IAPMS Joint Conference 2024 2024.7 International Association of Popular Music – Southeast Asia and Inter-Asia Popular Music Studies Group
Event date: 2024.7
Language:English Presentation type:Oral presentation (general)
Venue:มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Country:Thailand
-
History of Sound in the Arts in Japan: the case of "Onkyo-Chokoku" (meaning sound sculpture)
NAKAGAWA Katsushi
the 22th International Congress of Aesthetics International Congress of Aesthetics
Event date: 2023.7
Language:English Presentation type:Oral presentation (general)
Venue:Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Hrizonte, Brazil Country:Brazil
-
Kankyō Ongaku: How Brian Eno's ambient music has become known in 1980s Japan?
NAKAGAWA Katsushi
IASPM XXI 2022 2022.7 International Association for the Study of Popular Music
Event date: 2022.7
Language:English Presentation type:Oral presentation (general)
Venue:Daegu Country:Korea, Republic of
-
「Sound/Art」展(1984)のパースペクティヴ――〈サウンド・アートとは何か〉とは何か――
中川克志
第71回美学会全国大会 美学会
Event date: 2020.10
Language:Japanese Presentation type:Oral presentation (general)
Venue:オンライン(広島大学)
Preferred joint research theme 【 display / non-display 】
-
サウンド・アート研究(日本/アジア/概論)
-
Sound Studies
Charge of on-campus class subject 【 display / non-display 】
-
2025 Introduction to Socio-Cultural Critics
College of Urban Sciences
-
2025 Seminar on Sound Studies 1
College of Urban Sciences
-
2025 Seminar on Sound Studies 2
College of Urban Sciences
-
2025 Sound Studies
College of Urban Sciences
-
2025 Socio-Cultural Critics Studio A1
College of Urban Sciences
Charge of off-campus class subject 【 display / non-display 】
-
音楽
2024.4 Institution:東京理科大学
Level:Undergraduate (liberal arts)
-
複合文化論系演習(聴覚文化論)
2023.10 - 2025.3 Institution:早稲田大学
-
美学芸術学演習
Institution:國學院大學
-
音楽の思想
Institution:早稲田大学
Committee Memberships 【 display / non-display 】
-
創造都市横浜における創造的活動支援助成
2015.5 - 2016.2 創造的活動支援助成選考委員
Committee type:Academic society
-
創造都市横浜における創造的活動支援助成
2014.5 - 2015.2 創造的活動支援助成選考委員
Committee type:Academic society
Social Contribution(Extension lecture) 【 display / non-display 】
-
横浜サウンドスケープトークセッションに登壇
Role(s): Panelist
横浜コミュニティデザイン・ラボ 横浜サウンドスケープトークセッション 〜川崎義博・Marcos Fernandes・岩崎佐和・中川克志・中野圭とともに〜【オンライン視聴あり】 2025.8
-
KOIAS(神戸雰囲気学研究所)のアート・プロジェクトが開催するシンポジウムに登壇
Role(s): Lecturer
KOIAS(神戸雰囲気学研究所) thinking with ears 2025.5
-
特別講義: ベンジャミン・ピケット「トランスーション:ヘンリー・カウ、ロック、インプロヴィゼンーション、実験音楽、サウンドアートの発展史 」
Role(s): Guest
東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻 特別講義: ベンジャミン・ピケット「トランスーション:ヘンリー・カウ、ロック、インプロヴィゼンーション、実験音楽、サウンドアートの発展史 」 2024.9
-
ネットラジオ『毛利嘉孝のアート・リパブリック』に出演
Role(s): Guest
ネットラジオ『毛利嘉孝のアート・リパブリック』 2024.6
-
『サウンド・アートと実験音楽の間』VOL.3にてトーク+アルファ
Role(s): Guest, Commentator, Lecturer, Official expert, Performer
高円寺Fourth Floor II 『サウンド・アートと実験音楽の間』VOL.3 2023.11
Media Coverage 【 display / non-display 】
-
音響文化研究会トークイベント『音響メディア史』「13章 新しい楽器」
音響文化研究会 東京藝術大学美術学部中央棟第二講義室 2015.9
「#2 新しい「楽器」をつくる――録音と電子楽器以降の楽器 ゲスト 斉田一樹(木下研究所 客員所長)」に登壇
Academic Activities 【 display / non-display 】
-
日本ポピュラー音楽学会第34回年次大会シンポジウム「ポピュラー音楽研究と「音」というフィールド:現代東アジアの文脈におけるサウンド・スタディーズの可能性」
Role(s): Planning, management, etc., Panel moderator, session chair, etc.
中川克志 2022.12
Type:Competition, symposium, etc.