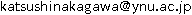|
所属組織 |
大学院都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 |
|
職名 |
准教授 |
|
生年 |
1975年 |
|
研究キーワード |
サウンド・アート、サウンド・スタディーズ、音響メディア論、音響文化論、現代音楽 |
|
メールアドレス |
|
|
ホームページ |
|
|
関連SDGs |
中川 克志 (ナカガワ カツシ)
NAKAGAWA Katsushi
|
|
|
代表的な業績 【 表示 / 非表示 】
-
【著書】 サウンド・アートとは何か : 音と耳に関わる現代アートの四つの系譜(ナカニシヤ出版) 2023年
【著書】 音響メディア史 2015年05月
【著書】 ジョナサン・スターン 2015(2003) 『聞こえくる過去:音響再生産の文化的起源』 2015年10月
直近の代表的な業績 (過去5年) 【 表示 / 非表示 】
-
【著書】 サウンド・アートとは何か : 音と耳に関わる現代アートの四つの系譜(ナカニシヤ出版) 2023年
【論文】 クリスチャン・マークレー再論:世界との交歓(東京都現代美術館(編) 2022 『クリスチャン・マークレー:トランスレーティング[翻訳する]』(東京都現代美術館、2021年11月20日-2022年2月23日) 展覧会図録 東京:左右社) 2022年04月
【論文】 日本における〈音のある芸術の歴史〉を目指して――1950-90年代の雑誌『美術手帖』を中心に――(細川周平(編)『音と耳から考える:歴史・身体・テクノロジー』(アルテスパブリッシング)) 2021年10月
【論文】 History of Sound in the Arts in Japan Between the 1960s and 1990s 2021年03月
【論文】 台湾におけるサウンド・アート研究試論──ワン・フーレイ(王福瑞、WANG Fujui)の場合── 2021年03月
プロフィール 【 表示 / 非表示 】
-
1975年生まれ。京都大学大学院文学研究科美学美術史学科博士課程修了。博士(文学)。
専門は音響文化論(サウンド・アート研究と音響メディア論)。
現在、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授。
都市科学部都市社会共生学科、横浜国立大学大学院都市イノベーション学府建築都市文化専攻都市文化系(芸術文化領域)、Y-GSCのスタッフ。
学内所属歴 【 表示 / 非表示 】
-
2011年4月-現在
専任 横浜国立大学 大学院都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 准教授
-
2017年4月-現在
併任 横浜国立大学 都市科学部 都市社会共生学科 准教授
-
2011年4月-現在
併任 横浜国立大学 大学院都市イノベーション学府 建築都市文化専攻 准教授
-
2011年4月-現在
併任 横浜国立大学 大学院都市イノベーション学府 都市イノベーション専攻 准教授
研究経歴 【 表示 / 非表示 】
-
サウンド・アート勃興期における音楽と美術とサウンド・アートの関係性の解明
科学研究費補助金
研究期間: 2024年4月 - 2027年3月
-
東アジアの事例に基づくサウンド・アート研究の基盤の確立
科学研究費補助金
研究期間: 2020年4月 - 2024年3月
-
台湾における「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」の系譜の研究:王福瑞の事例を中心に
民間学術研究振興費補助金
研究期間: 2019年4月 - 2020年3月
-
日本におけるサウンド・アートの成立過程の調査
研究期間: 2015年4月 - 2018年3月
-
クリスチャン・マークレイ研究—サウンド・アートの系譜学
科学研究費補助金
研究期間: 2012年4月 - 2015年3月
著書 【 表示 / 非表示 】
-
サウンド・アートとは何か : 音と耳に関わる現代アートの四つの系譜
中川 克志( 担当: 単著)
ナカニシヤ出版 2023年12月 ( ISBN:9784779517730 )
記述言語:日本語 著書種別:学術書
-
音響メディア史
谷口文和、中川克志、福田裕大( 担当: 共著 , 範囲: 5,6,10,12,13, 15章を担当)
ナカニシヤ出版 2015年5月 ( ISBN:9784779509513 )
総ページ数:334 記述言語:日本語 著書種別:学術書
2015年5月5日 初版第一刷
担当章は全15章321頁中6章:5章:81-100,6章:100-118,10章:181-198,12章:219-240,13章:241-262,15章:281-302 -
サウンド&アート展 : 見る音楽、聴く形 = sound & art : performance/workshop
毛利 嘉孝, 中川 克志, 廣川 暁生, 明石 薫, クリエイティブ・アート実行委員会( 担当: 単著)
クリエイティブ・アート実行委員会2021 2021年
記述言語:日本語 著書種別:一般書・啓蒙書
-
Computational Aesthetics(SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology)
Yasuhiro Suzuki, Katsushi Nakagawa, Takashi Sugiyama, Fuminori Akiba, Eric Maestri, Insil Choi, and Shinya Tsuchiya.( 担当: 共著 , 範囲: A Brief Consideration About the Relationship Between Sound Art and Tactile Sense.)
Springer 2018年9月 ( ISBN:9784431568421 ) [査読有り]
総ページ数:96 担当ページ:53-65 記述言語:英語 著書種別:学術書
NAKAGAWA Katsushi. 2018. "A Brief Consideration About the Relationship Between Sound Art and Tactile Sense." In: Computational Aesthetics. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Tokyo: 53-65.
-
アメリカ文化事典:アメリカ学会(編)
アメリカ学会(編)( 担当: 共著 , 範囲: 「実験音楽」(「17.音楽・舞台」収録))
丸善出版(東京) 2018年1月 ( ISBN:9784621302149 )
総ページ数:960 担当ページ:692-693 記述言語:日本語 著書種別:事典・辞書
学位論文 【 表示 / 非表示 】
-
聴くこととしての音楽―ジョン・ケージ以降のアメリカ実験音楽研究
中川 克志
2008年3月
学位論文(博士) 単著
京都大学大学院文学研究科(2008年3月24日 京都大学博士(文学)取得 文博第418号)
-
スティーヴ・ライヒにおけるミニマリズムについて―初期作品の考察
中川 克志
2000年3月
学位論文(修士) 単著
京都大学大学院文学研究科(2000年3月23日 京都大学修士(文学)取得 文修第3272号)
論文 【 表示 / 非表示 】
-
中川 克志
関西美学音楽学論叢 9 2 - 20 2025年3月 [招待有り]
担当区分:筆頭著者 記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要) 単著
-
音楽認識論序説 ジョン・ケージ以降の音と音楽の境界線をめぐって[2/2]
中川 克志
常盤台人間文化論叢 11 ( 1 ) 107 - 123 2025年3月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要) 出版者・発行元:横浜国立大学都市イノベーション研究院 単著
(紙面の都合上、本年度は本論文の前半部分のみを掲載する。後半部分は次号に掲載予定である。ただし、以下の要旨は論文全体の要旨である。)
本論文は、1950年代にジョン・ケージによって行われた「革命」以降の、音と音楽の境界設定の歴史とメカニズムについて検討する。ケージは音の遍在性という観念を強調し、音楽活動の領域内部にあらゆる音響を取り込もうとした。本論文では、そこで設定された音と音楽との境界線について精査するために、ケージがなし得た貢献の限界を評価する。本論では、ケージが設定した〈あらゆる音は音楽になり得る〉という原則が、〈あらゆる音は音楽である〉と解釈されてきたことを指摘する。その事例として、本論では、1970年代に環境音を音楽の領域に取り込んだ三つの動向を検討する。ケージには追随する者だけではなく反発する者もいたが、反発するものは二分される。一方は音楽の伝統的な領域を確保し、ケージ的な実験音楽をそこから排除しようとする(クリス・カトラー)が、他方で、音の芸術(あるいはサウンド・アート)という独自領域を設定してそこからケージ的な活動を排除する者もいる(ダン・ランダー)。この論理操作の規定に流れる概念操作を「音の音楽化」と呼べることを、本論では指摘している。
本論は、音響連続体とケージ的な実験音楽との関係を支配する認知的な枠組みを精査する。そうすることで、音と音楽とをめぐる実験音楽以降の言説を歴史的な系譜の内部で理解し、音と音楽との境界線を強調する議論は終止符を打つべきだ、と主張する。私たちは、音と音楽との境界線を過剰に重視することなく、新しい実践と対話を育んでいくべきである。 -
音楽認識論序説 ジョン・ケージ以降の音と音楽の境界線をめぐって[1/2]
中川 克志
常盤台人間文化論叢 10 ( 1 ) 145 - 160 2024年3月
記述言語:日本語 掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要) 出版者・発行元:横浜国立大学都市イノベーション研究院 単著
(紙面の都合上、本年度は本論文の前半部分のみを掲載する。後半部分は次号に掲載予定である。ただし、以下の要旨は論文全体の要旨である。)
本論文は、1950年代にジョン・ケージによって行われた「革命」以降の、音と音楽の境界設定の歴史とメカニズムについて検討する。ケージは音の遍在性という観念を強調し、音楽活動の領域内部にあらゆる音響を取り込もうとした。本論文では、そこで設定された音と音楽との境界線について精査するために、ケージがなし得た貢献の限界を評価する。本論では、ケージが設定した〈あらゆる音は音楽になり得る〉という原則が、〈あらゆる音は音楽である〉と解釈されてきたことを指摘する。その事例として、本論では、1970年代に環境音を音楽の領域に取り込んだ三つの動向を検討する。ケージには追随する者だけではなく反発する者もいたが、反発するものは二分される。一方は音楽の伝統的な領域を確保し、ケージ的な実験音楽をそこから排除しようとする(クリス・カトラー)が、他方で、音の芸術(あるいはサウンド・アート)という独自領域を設定してそこからケージ的な活動を排除する者もいる(ダン・ランダー)。この論理操作の規定に流れる概念操作を「音の音楽化」と呼べることを、本論では指摘している。
本論は、音響連続体とケージ的な実験音楽との関係を支配する認知的な枠組みを精査する。そうすることで、音と音楽とをめぐる実験音楽以降の言説を歴史的な系譜の内部で理解し、音と音楽との境界線を強調する議論は終止符を打つべきだ、と主張する。私たちは、音と音楽との境界線を過剰に重視することなく、新しい実践と対話を育んでいくべきである。 -
日本におけるサウンド・アートの系譜学:神戸ジーベックホール(1989-1999)をめぐって:その1――『Sound Arts』誌(1992-1998)の場合――
中川 克志
Cross sections : 京都国立近代美術館研究論集 11 44 - 53 2024年
記述言語:その他外国語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 単著
-
日本におけるサウンド・アートの系譜学:神戸ジーベックホール(1989-1999)をめぐって:その1――『Sound Arts』誌(1992-1998)の場合――
中川 克志
京都国立近代美術館研究論集 CROSS SECTIONS 11 44 - 53 2024年
記述言語:その他外国語 掲載種別:研究論文(学術雑誌) 単著
総説・解説記事等 【 表示 / 非表示 】
-
ジョナサン・スターン 2015(2003) 『聞こえくる過去:音響再生産の文化的起源』
中川克志・金子智太郎・谷口文和(訳)
インスクリプト 60 - 75 2015年
記述言語:日本語 掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他) 共著
-
[書評] 庄野進著『聴取の詩学 枠と出来事 庄野進音楽美学論集』(春秋社、2024年)
中川克志
週刊読書人 ( 20250314号 ) 2025年3月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等 単著
-
[翻訳]ジョナサン・スターン+メハク・ソーニー「アクースマティックな問いとデータ化の意志——Otter.ai・低リソースな言語・機械聴取のポリティクス」
ジョナサン・スターン, メハク・ソーニー, 中川克志
学術誌『メディウム』 5 163 - 196 2024年12月
記述言語:日本語 掲載種別:その他 単著
-
[書評] 豊田泰久(語り手)、林田直樹(聞き手)、潮博恵(解説)『コンサートホール×オーケストラ 理想の響きをもとめて』(アルテスパブリッシング、2024年)
中川克志
週刊読書人 ( 20240607号 ) 2024年6月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等 単著
-
座談会 「音」と文学――文学研究とサウンド・スタディーズとの対話――
福田貴成、中川克志、疋田雅章、広瀬正
昭和文学研究 88 2 - 23 2024年3月 [依頼有り]
記述言語:日本語 掲載種別:速報,短報,研究ノート等(学術雑誌) 単著
作品・芸術・データベース等 【 表示 / 非表示 】
-
三沢洋紀と岡林ロックンロール・センター『サイレントのとんがり』
三沢洋紀、岡林コゾー、中川克志、宮地健作
2013年9月 - 現在
作品分類:芸術活動 発表場所:Headz
羅針盤、渚にてと並び関西三大うたものバンドと称されたラブクライの中心人物で、ラブクライ活動休止後はPONY、LETTER、三沢洋紀とゆふいんの森、真 夜中ミュージックといったバンドで活動し、昨年は柴田聡子の1stアルバム『しばたさとこ島』、今年は都市レコード『road to you』のプロデューサーとして、その音楽的才能を遺憾無く発揮した三沢洋紀。
彼が、THE BITE / U.G MANの岡林コゾウ大輔、OKミュージックボールの中川克志、ラブクライのメンバーでもあった宮地健作と結成したバンド、三沢洋紀と岡林ロックンロール・ センターが、2012年7月発売のCD-Rの8曲入りアルバム『三沢洋紀と岡林ロックンロール・センター』に続き、ファースト・フル・アルバムを完成させた。
三沢洋紀にとって、プレスCDとしては2012年2月発売の『真夜中ミュージック』(限定300枚)、全国流通盤としては2009年の『三沢洋紀とゆふいんの森』以来となる本作は、プロデューサーにKIRIHITO、GROUP、younGSoundsのメンバーとして、刺激的なサウンドを追求し続けている竹久圏を起用。予てからお互いの活動に注目していたという二人がここ数年で急接近し、三沢にとっては念願の竹久とのコラボレートが実現する こととなった。
ラブクライ時代から定評のある三沢のソングライティング能力やポップ・センスは更に磨かれ、ギター・プレイヤーとしても参加した竹久のハードコアやクラブシーンにも精通した不良性の高い歪な音像やリズム・センス、ジャンルを超越したオルタナティヴなエッセンスによって、単なるうたも の作品では味わうことの出来ない多彩な魅力が詰まった傑作アルバムとなった。
録音、ミックス、マスタリングは近年のテニスコーツやマジキック作品には欠かせない存在となっているサウンド・アーティスト、大城真が担当。
三沢の甘いヴォーカルといぶし銀なバンド・アンサンブルによる、アーシーかつアーバンというアンビヴァレンツなサウンドが奇跡的に融合した、今の日本では他に例を見ない、洒脱な大人のロックンロール・アルバムに仕上がっている。
人生の酸いも甘いも知り尽くした男達が奏でる、この豊潤なバンド・サウンドにどっぷりと酔いしれて欲しい。
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
サウンド・アート勃興期における音楽と美術とサウンド・アートの関係性の解明
研究課題/領域番号:24K03444 2024年4月 - 2027年3月
基盤研究(C)
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
本研究は、日本と台湾と欧米でサウンド・アートが注目され始めた時期(サウンド・アートの勃興期)における個別事例を研究する。それらが音楽や美術といった既存の周辺諸領域といかなる関係性を取り結ぶことになったか、ということに留意しながら、個別事例研究を蓄積し、比較考察する。サウンド・アートという現象がその勃興期に周辺諸領域と取り結んだ関係性を問うことで、現代アートにおけるサウンド・アートという現象の歴史的意義の解明に貢献すること。これが本研究の目的である。
-
東アジアの事例に基づくサウンド・アート研究の基盤の確立
2020年4月 - 2024年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
代表者:中川克志
資金種別:競争的資金
本研究は〈東アジアの事例に基づいてサウンド・アート研究の基盤を確立すること〉を目指す。東アジア、とりわけ台湾の事例を比較対象として取りあげ、日本におけるサウンド・ アートの系譜と比較研究し、その成果を国際的な視野のもとで考察することで、アジア圏のサウンド・アートの独自性を見出し、間アジア的なパースペクティヴからサウンド・アートという対象に総合的にアプローチする。欧米の事例ではなくアジア圏の事例を中心に、総合的なサウンド・アート研究を構想すること、これが本研究の目的である。
-
サウンドアート学確立による20世紀アート史の書き換え
2018年6月 - 2021年3月
科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究
代表者:中川眞(大阪市立大学 都市研究プラザ 特任教授)
資金種別:競争的資金
課題番号:18K18488
研究分野:中区分1:思想、芸術およびその関連分野
研究機関:大阪市立大学 -
日本におけるサウンド・アートの成立過程の調査
2015年4月 - 2018年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
代表者:中川 克志
資金種別:競争的資金
本研究「日本におけるサウンド・アートの成立過程の調査」の目的は、日本においてサウンド・ アートが登場してきた経緯の調査である。「サウンド・アート」という言葉が盛んに使われるよう になった 19 80 年代を中心に、(1)インタビュー調査 と(2)文献調査を行う。日本におけるサウ ンド・アートの登場に関す る先行研究はほとんど存在しないため、本研究では基礎的な資料の収 集整備を重視する。また、その成果を、 日本より 10 年ほど遅れてサウンド・アートを制作するよ うになった(3)台湾、香港、韓国などの状況と比較す ることで、日本におけるサウンド・アート の文化的位置づけの独自性の考察を試みる。これらの研究を通じて 、「日本におけるサウンド・ アート」に関する研究と、日本における「サウンド・アートに関する研究」に貢 献したい。
-
パーソナル・ファブリケーション以降の芸術表現に向けた視聴覚メディアの系譜学
2015年4月 - 2017年3月
科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究
代表者:城一裕(情報科学芸術大学院大学・メディア表現研究科・講師)
資金種別:競争的資金
課題番号:15K12842
研究分野:人文学, 芸術学, 芸術一般
研究機関:情報科学芸術大学院大学
その他競争的資金獲得・外部資金受入状況 【 表示 / 非表示 】
-
台湾における「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」の系譜の研究:王福瑞の事例を中心に
2019年4月 - 現在
民間財団等 稲盛研究助成
代表者:中川克志
本研究は、1990年代初頭に始まった台湾における「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」の歴史について、その始まりから現在に至る系譜を明らかにしようとするものである。本研究では、台湾におけるサウンド・アートのパイオニアの一人である王福瑞の活動を中心に調査する。彼の活動を軸として予備調査に基づいてリストアップした「2.内容」の人々にインタビュー調査を行うことで、90年代から現在に至る台湾におけるサウンド・アートの概要を明らかにできるだろう。この領域の研究はまだほとんど整備されておらず、本研究には一次資料を準備するという意義がある。
台湾におけるサウンド・アートの特徴は、戒厳令が解除された90年代以降に展開したことである。また、日本や欧米では「サウンド・アート」と呼ばれる音を用いる視覚美術だけではなく、日本や欧米で80年代頃に登場した「ノイズ・ミュージック」と呼ばれる音楽もまた、「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」という名称で言及されることも特徴である。これらの特徴は、日本、香港、欧米、中華人民共和国等の相互影響関係の中から生じたトランスナショナルな性格を示すものとして、重要である。本研究には、アジア諸国の文化の相互影響関係の事例研究である、という意義もある。
それゆえ、本研究は、まず第一に、台湾における「サウンド・アート(聲音藝術、sound art)」の系譜において諸活動がどのような布置を形成しているかを探り、第二に、それらがアジア諸国のなかでどのようなトランスナショナルな力学のもとで形成されてきたのか、ということを明らかにしたい。本研究は、究極的には、アジアにおける西洋化と近代化にかかわる文化のメカニズムの解明に貢献せんとするものである。
研究発表 【 表示 / 非表示 】
-
NAKAGAWA Katsushi
국제학술대회가 성황리에 마무리되었습니다.함께해주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 아래에 학술대회 현장의 사진을 공유합니다. 2025年3月
開催年月日: 2025年3月
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
国名:大韓民国
-
The comparative study between environmental music in 1980s Japan and Kankyō Ongaku in 2010s Japan
NAKAGAWA Katsushi
IASPM-SEA & IAPMS Joint Conference 2024 2024年7月 International Association of Popular Music – Southeast Asia and Inter-Asia Popular Music Studies Group
開催年月日: 2024年7月
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 国名:タイ王国
-
History of Sound in the Arts in Japan: the case of "Onkyo-Chokoku" (meaning sound sculpture)
中川克志
the 22th International Congress of Aesthetics International Congress of Aesthetics
開催年月日: 2023年7月
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Hrizonte, Brazil 国名:ブラジル連邦共和国
-
Kankyō Ongaku: How Brian Eno's ambient music has become known in 1980s Japan?
NAKAGAWA Katsushi
IASPM XXI 2022 2022年7月 International Association for the Study of Popular Music
開催年月日: 2022年7月
記述言語:英語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:Daegu 国名:大韓民国
-
「Sound/Art」展(1984)のパースペクティヴ――〈サウンド・アートとは何か〉とは何か――
中川克志
第71回美学会全国大会 美学会
開催年月日: 2020年10月
記述言語:日本語 会議種別:口頭発表(一般)
開催地:オンライン(広島大学)
担当授業科目(学内) 【 表示 / 非表示 】
-
2025年度 社会文化批評基礎論
都市科学部
-
2025年度 音響文化論演習Ⅰ
都市科学部
-
2025年度 音響文化論演習Ⅱ(日本語)
都市科学部
-
2025年度 音響文化論講義
都市科学部
-
2025年度 社会文化批評スタジオAⅠ
都市科学部
担当経験のある授業科目(学外) 【 表示 / 非表示 】
-
音楽
2024年4月 - 現在 機関名:東京理科大学
科目区分:学部教養科目
-
複合文化論系演習(聴覚文化論)
2023年10月 - 2025年3月 機関名:早稲田大学
-
美学芸術学演習
機関名:國學院大學
-
音楽の思想
機関名:早稲田大学
委員歴 【 表示 / 非表示 】
-
創造都市横浜における創造的活動支援助成
2015年05月 - 2016年2月 創造的活動支援助成選考委員
委員区分:学協会
-
創造都市横浜における創造的活動支援助成
2014年05月 - 2015年2月 創造的活動支援助成選考委員
委員区分:学協会
社会活動(公開講座等) 【 表示 / 非表示 】
-
横浜サウンドスケープトークセッションに登壇
役割:パネリスト
横浜コミュニティデザイン・ラボ 横浜サウンドスケープトークセッション 〜川崎義博・Marcos Fernandes・岩崎佐和・中川克志・中野圭とともに〜【オンライン視聴あり】 2025年8月
-
KOIAS(神戸雰囲気学研究所)のアート・プロジェクトが開催するシンポジウムに登壇
役割:講師
KOIAS(神戸雰囲気学研究所) thinking with ears 2025年5月
-
特別講義: ベンジャミン・ピケット「トランスーション:ヘンリー・カウ、ロック、インプロヴィゼンーション、実験音楽、サウンドアートの発展史 」
役割:出演
東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻 特別講義: ベンジャミン・ピケット「トランスーション:ヘンリー・カウ、ロック、インプロヴィゼンーション、実験音楽、サウンドアートの発展史 」 2024年9月
-
ネットラジオ『毛利嘉孝のアート・リパブリック』に出演
役割:出演
ネットラジオ『毛利嘉孝のアート・リパブリック』 2024年6月
-
『サウンド・アートと実験音楽の間』VOL.3にてトーク+アルファ
役割:出演, コメンテーター, 講師, 情報提供, 実演
高円寺Fourth Floor II 『サウンド・アートと実験音楽の間』VOL.3 2023年11月
メディア報道 【 表示 / 非表示 】
-
音響文化研究会 京都市中京区MEDIASHOP 2015年10月
「#3 「紙のレコード」の作られ方 ゲスト 城一裕(情報科学芸術大学院大学 [IAMAS] 講師)の司会
-
音響文化研究会トークイベント『音響メディア史』「13章 新しい楽器」
音響文化研究会 東京藝術大学美術学部中央棟第二講義室 2015年9月
「#2 新しい「楽器」をつくる――録音と電子楽器以降の楽器 ゲスト 斉田一樹(木下研究所 客員所長)」に登壇
学術貢献活動 【 表示 / 非表示 】
-
日本ポピュラー音楽学会第34回年次大会シンポジウム「ポピュラー音楽研究と「音」というフィールド:現代東アジアの文脈におけるサウンド・スタディーズの可能性」
役割:企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等
中川克志 2022年12月
種別:大会・シンポジウム等